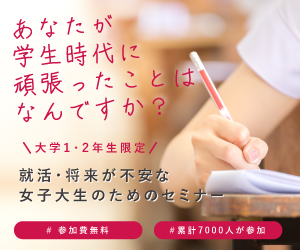「念頭に置く」の意味とは?
「念頭に置く」は、いつも忘れないでいる、常に心にかけるというような意味があります。
「念頭」の意味は、心の中にある想いや考え、胸や心のうちということです。
「念」の意味は、注意や思いということです。
「頭」の意味は、思考や考えということです。
そのため、「念頭に置く」は、いつも忘れないで心がけること、考えていることになります。
「念頭に置く」は、胸や心に置いておく、つまり記憶に留める、心がけるという意味になります。
頭の片隅に必須事項や注意点などを置いて、行動すべきときにも該当します。
「念頭に置く」の使い方とは?
ここでは、「念頭に置く」の使い方についてご紹介します。
自分が決意を表すときと目下・対等の人に注意するときに使う
「念頭に置く」を使うのは、自分が決意を表すときと目下・対等の人に注意するときです。
「念頭に置く」を自分が決意を表すときに使う例文としては、次のようなものなどがあります。
- 「いつ災害は発生してもおかしくないということを念頭に置いて行動する。」
- 「教師に習ったアドバイスを念頭に置いて、試験勉強を行う。」
- 「スムーズに海外の取引先とやり取りする方法は、文化や価値観の違いを念頭に置くことである。」
- 「念頭に置く」を目下・対等の人に注意するときに使う例文としては、次のようなものが違います。
- 「作業を行うときは、先に注意したことを念頭に置いてください。」
- 「社員の全てが使うことを念頭に置いて検討して欲しい。」
「念頭に入れる」は使わない
「念頭に置く」は、よく「念頭に入れる」と間違って使われています。
意見としては間違いではないというものもありますが、現時点では使わないようにしましょう。
「念頭に入れる」は、「頭に入れる」と間違って誕生した言葉ということで、間違っているとされています。
「念頭に置く」の敬語表現とは?
ここでは、「念頭に置く」の敬語表現についてご紹介します。
「お含みおきください」
「念頭に置く」は、ビジネスシーンで取引先や目上の方、顧客に使う敬語としては推奨されていません。
ビジネスシーンでよく使われており、丁寧な敬語の「お含みおきください」方がいいでしょう。
「お含みおきください」は、事情を理解して記憶しておいてくださいという意味です。
「お含みおきください」を使った例文としては、次のようなものなどがあります。
- 「お客様の都合による日程変更・キャンセルは、キャンセル料が発生しますことをお含みおきください。」
- 「恐縮ですが、明日はお休みさせていただきます。どうぞお含みおきください。」
ビジネスシーンでは「常に念頭に置く」は使わない
かしこまったビジネスシーンでは、「常に念頭に置く」は使わない方が良いでしょう。
というのは、もともと「念頭に置く」には、いつも、常にという意味があり、重言になるためです。
重言というのは、意味が同じ言葉を重ねるもので、重複表現や二重表現ともいいます。
基本的に、間違った使い方ですが、強調表現や慣用句として、また意味がよくわかるようにするために使うときもあります。
例えば、事前予約のときは、予約の意味には事前にということがありますが、間違っていると思わないで使っているときが多くあります。
しかし、ビジネスシーンでは重言を止める方がいいでしょう。
「念頭に置く」の類義語とは?
ここでは、「念頭に置く」の類義語についてご紹介します。
「頭に入れる」
「頭に入れる」は、意味が「念頭に置く」と似ているため、「念頭に入れる」と間違いやすいものです。
「頭に入れる」の意味は、よく理解して記憶しておくということです。
例えば、「方法を頭に入れておく」や「日程を頭に入れておく」などで、よくビジネスシーンで使われます。
「念頭に置く」とは、頭の中にあることを留めるということで同じです。
記憶するという意味が、「頭に入れる」には含まれています。
一方、「念頭に置く」は、いつも意識したいことに使われるため、記憶するという意味は含まれていません。
「念頭に置く」と「頭に入れる」は、意味合いが違うため注意しましょう。
「心に留める」
「心に留める」の意味は、いつも意識して忘れないということです。
そのため、ほとんど「念頭に置く」と同じ意味でしょう。
しかし、「心に留める」は、過去の出来事に使われるときが多くあります。
一方、「念頭に置く」は、今からの出来事に意識したいことをいうときに使われます。
使い方にこのような違いがありますが、明確に決まっているということではありません。
「心に留める」を使った例文としては、次のようなものなどがあります。
- 「大学に受かったのは、他の人の助けがあったことも心に留めておいて欲しい。」
- 「現在の自分があるのは、父親のおかげであるということを心に留めておきたい。」
この例文からもわかるように、「心に留める」は過去の出来事に使われます。
「肝に銘じる」
「肝に銘じる」の意味は、強く心に刻んで忘れないということです。
臓器の中でも、「肝」は大切な役割がある肝臓になります。
ここから、「肝」といえば大切な部分・事をいうようになりました。
例えば、「肝に銘じる」を使った例文としては、「上長のアドバイスを肝に銘じて、立派に社会人として成長しよう」などがあります。
「肝に銘じる」の方が、「念頭に置く」よりも強く意識しているという意味合いがあります。
意味はほとんど同じですが、物事の重要度に応じて使いわける必要があります。
なお、「肝に命じる」という言葉もありますが、「命じる」の意味合いは「言い聞かせる」ということであるため間違っています。
「念頭に置く」の英語表現とは?
ここでは、「念頭に置く」の英語表現についてご紹介します。
「bear in mind」
「bear」の意味は、名詞では熊になりますが、動詞では抱くになります。
「im mind」の意味は心の中でということであるため、「bear in mind」の意味は心の中に抱くということになります。
「bear in mind」を使った例文としては、次のようなものがあります。
- 「Bear those words in mind.」(その言葉を念頭に置く。)
「keep in mind」
「keep」の意味は、いつまでもしまっておく、持っている、ということです。
そのため、「keep in mind」の意味は、心の中にしまっておくということになります。
このように、「bear」と「keep」のいずれを使っても、意味が同じになります。
心の中にしまっておく、抱くという意味があり、「念頭に置く」の英語表現として使われるため、慣用句の意味を把握しておきましょう。