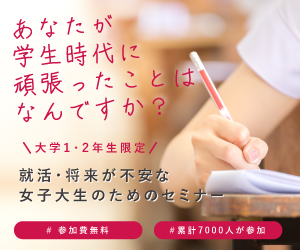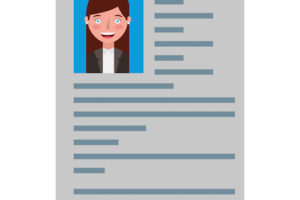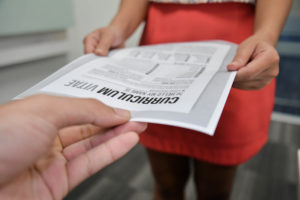履歴書には、いくつか年号を書く項目があります。こういった年号をうっかり間違えてしまうと、思いのほか大ごとになってしまうこともありますので要注意です。今回は、履歴書の年号の書き方のルールについて紹介していきましょう。
履歴書の年号の基本的なポイント!どんなときに年号を使うものなの?
履歴書に年号を記入する必要があるのが、次のような項目です
- 履歴書の記入日、申込日
- 生年月日
- 学歴
- 職歴
氏名欄の上には、日付を入れる欄が設けられていることが多いです。ちなみに、この欄には履歴書を記入した日、または応募をする日の日付を記入します。日付は年号から記入しますので、こちらの欄を書くときにはその年の年号を正確に把握しておく必要があります。また、生年月日も生まれた年の年号から書くのが一般的です。生年月日の年号は、採用担当者が年齢を確認するときにチェックする部分と言えます。年号がとくに重要になってくるのが、学歴や職歴を書くときです。学歴や職歴を書く欄の左側には、年月日を記入する項目が設けられているため、1つの経歴を記載するごとに年号を書き込む作業が発生するでしょう。このほかにも、保有資格や免許を記載する項目で、年号を入れる必要がでてきます。
【履歴書の年号の書き方1】和暦と西暦ならどちらを選ぶべきなのか
履歴書に年号を書く場合、和暦と西暦のどちらを選べばいいかで迷ってしまうかもしれません。この部分でつまずいてしまうと、履歴書を書く作業が進まなくなってしまいますので、書き始める前に書き方のルールをひととおり把握しておきましょう。
和暦、西暦のいずれでも問題はない
年号を記入するときには、和暦、西暦の2つの選択肢から好きなほうを選ぶことができます。例えば、和暦の年号しかわからないような場合、とくに指定がなければ、あらためて西暦の年号に直す必要はありません。このようなときには、知っている和暦の年号をそのまま履歴書に書いても問題はないでしょう。
和暦、西暦ならどちらのほうがいいという決まりはない
履歴書の場合、和暦、西暦のどちらのほうが適しているという決まりはありません。これらの年号は、いずれも公的な文書で広く使われていますので、どちらを書いても採用、不採用に響くといったことはないです。
【履歴書の年号の書き方2】年号の表記は統一しなければならない
履歴書の年号を書く際には、書類を読む採用担当者がわかりやすいような書き方をすることが大切です。以下のようなポイントを意識しておくと、わかりやすく年号を記載できるでしょう。
和暦と西暦のいずれかに統一する
いったん、和暦と西暦のどちらかを選んだら、すべての項目をその表記で書くのが履歴書のルールです。和暦と西暦が入り混じっていると、内容がわかりにくくなるうえに、統一感がない履歴書になってしまいます。「読む人への配慮が足りない」と判断されることもあるため、表記はいずれかに統一しましょう。
年号が印字されているときにはその内容に合わせる
履歴書にあらかじめ年号が印字されているような場合は、ほかの部分もその年号に統一して記入をしたほうがいいでしょう。履歴書としての統一感をだすためにも、年号の表記は1つに絞ることが大切です。
【履歴書の年号の書き方3】略した表記で年号を書くのはNG行為
公的な書類の場合も、年号を略して記入するケースが見られるようになりました。こういった書き方は、文字のスペースを少なくできる、などのメリットがありますが、履歴書を書くときには避けた方が無難です。履歴書での文字の省略はマナー違反ですので、正確な年号を記入しましょう。例えば、以下のような書き方は履歴書には適していません。
- S60(昭和60年)
- H5(平成5年)
急いで履歴書を仕上げる必要があるときなどは、つい省略のスタイルで年号を書いてしまう人もいるかもしれません。このようにアルファベットで年号を略した場合、全く内容を理解してもらえないといったわけではありませんが、採用担当者に与える印象はかなり悪くなります。「常識がない」と思われてしまう可能性が高いため、書類選考でも不利になってしまうかもしれません。昭和や平成などの年号を書く場合は、省略をせずにきちんと漢字で記入をしましょう。
【履歴書の年号の書き方4】繰り返しの表現の使用は避けたほうがいい
入学と卒業が同じ年の場合には、年号の部分に「〃(繰り返し)」という表現を使う人もいます。「何度も同じ内容を書く必要はない」と考えて、このような書き方をするケースが多いですが、これも年号の略称の一つであるため履歴書に使用するのは避けたいところです。「〃(繰り返し)」の表現で省略をしてしまうと、次のようなデメリットがあります。
- 履歴書の書き方を知らないと思われる
- 空欄が目立ってしまう
- 読んだ人が内容を理解するのに少し時間がかかる
年号の部分に限らず、履歴書に「〃(繰り返し)」のような省略の記号を書くのはマナー違反と言えます。履歴書の書き方のルールをわきまえていない、と採用担当者に受け取られてしまうと、評価にもダイレクトに響いてきます。また、年号の部分に省略の記号を書くと、空欄が目立ってしまうのも難点です。履歴書は、目にしたときの第一印象も大切です。空欄が多いと、「意欲が感じられない」とマイナスの評価を受けてしまうかもしれません。省略しないで記載してある場合に比べて、経歴の内容を理解するのに時間がかかる点も1つの問題です。
【履歴書の年号の書き方5】スラッシュを使った表現は避けたほうがいい
年月日の表記をする際に、以下のようなスタイルで「/(スラッシュ)」を付けるのも避けたほうがいいでしょう。この手の記号も、履歴書を書くときには使わないのが基本です。
- 「2000/1/1」(2000年1月1日)
- 「平成15/1/1」(平成15年1月1日)
「/(スラッシュ)」は、パソコンや携帯電話などに表示される年号にも使われているため、履歴書を書くときにうっかり使ってしまうケースもあるかもしれません。しかしながら、この「/(スラッシュ)」の場合も省略記号と同様に履歴書には相応しくありません。年号の年月日の部分は、すべて漢字で記載するのが一般的な履歴書のマナーですので、記号を使うとマイナスの評価につながってしまうことがあります。外資系企業の求人に応募をする際にも、こういった基本的なマナーは守ったほうがいいでしょう。
【履歴書の年号の書き方6】応募書類の指示に年号の指定があれば従う
応募書類は、募集要項などで書き方のルールが指示されていることがあります。このような場合は、応募先の指示に従うのがベストです。
「年号は和暦で記載すること」といった指示がある場合は和暦にする
例えば、「和暦で記載すること」など、何らかの指示があるときには、応募をする日付や生年月日などもすべて和暦にする必要があります。特別な指示がある場合、応募先の会社が扱いやすいような表記を推奨していることが多いです。
指示を守らないとデータの登録の際に手間がかかる場合がある
「和暦にすること」と指定があるにもかかわらず、西暦で記載してしまった場合には、担当者の作業が煩雑になる可能性があります。例えば、会社が従業員のデータベースに個人データを登録するときなどに、1つ1つ西暦を和暦に直さなければならなくなります。表記を統一するために年号を1つひとつ換算する必要がでてくるため、作業にも手間がかかるでしょう。こういった状況を避けるためにも、指示があるときには必ず指定に従うべきと言えます。
入学や卒業の年号を覚えていないときはどうすればいいものなの?
生年月日などは西暦、和暦の年号を両方とも把握している人が多いですが、学校に入学した年や卒業した年の年号については、曖昧な記憶しかない人も少なくありません。実のところ、うろ覚えの状態で履歴書の年号を記入するのは間違いのもとです。すぐに正確な年号が頭に浮かんでこないというときには、以下のような方法を試してみましょう。
- 入学時と卒業時の年齢から逆算する
- 年号早見表で年号をチェックする
例えば、入学や卒業をした時点の年齢から逆算をするという方法があります。応募する時点の年齢から入学、卒業した時の年齢を引くと、経過した年数がわかります。応募する時点の西暦や和暦の年号から経過年数を引けば、当時の年号が割り出せるでしょう。また、履歴書に付いている年号早見表などを利用するのも1つの方法です。このような年号早見表には、西暦と和暦がそれぞれ記載されていますので、該当する部分をチェックしてみましょう。
和暦と西暦の変換がすぐにできる!簡単に年号がわかる計算方法は?
和暦と西暦の変換をするときには、パターンに合わせていくつかの計算式が使えます。こういった計算式を使うと、年号早見表が手元になくてもすぐに年号を書けますので、いざというときのために覚えておくと便利です。
平成から西暦に変換する
平成の年号から西暦に変換したいときには、平成の年号から12を引いて2000を足します。
西暦から平成に変換する
西暦の年号を平成に変えたい場合は、西暦の年号に12を足します。この計算式で出た合計の下二桁が、平成の年号です。
昭和から西暦に変換する
昭和の年号から西暦に変換する際には、昭和の年号に25を足していきます。西暦の年号は、合計値の下二桁です。
西暦から昭和に変換する
西暦の年号を昭和になおすときは、西暦の年号から25を引きましょう。合計の下二桁が、昭和の年号です。
年号を間違えてしまうことで起こる影響は?記載ミスを避けるべき理由
実のところ、年号を書き間違えて記入してしまっても、「特に大きな問題にならないのでは」と思うかもしれません。「少しぐらい間違えても気付かれない」と高を括って、そのまま訂正をしないで放置してしまう人もいるでしょう。しかしながら、採用担当者は、思いのほか細かなところまでチェックしているものです。年号が合っていないことに万が一気付かれれば、「不注意な人」と判断されてしまう可能性があるため、注意をしましょう。
- 正確な年齢や経歴を把握しにくくなる
- 「故意に事実と異なる内容を書いたのでは」という疑念が生まれる
年号を書き間違えてしまうと、例えばこのような問題が生じてきます。応募者から訂正の申し出がない限り、提出した履歴書の内容をもとに採用担当者は事実を確認しますので、内容が実際の状況と異なると正確な経歴などが把握しにくくなってしまいます。「故意に事実と違った年号を書いたのではないか」といった疑いを持たれる可能性もあるため、記載ミスをするのはできるだけ避けたほうがいいわけです。
履歴書の学歴欄はいつから書くべきもの?中卒と高卒のどちらが正解なの?
履歴書の学歴欄を書くときには、どの時点から書けばいいかで迷うケースもあります。学歴欄は、応募する人の状況によって最適な書き方が変わりますので、自分の立場に合った方法をチェックしておきたいところです。
就活生の場合
就職活動中の学生の場合は、中学校を卒業した年から年号を書くのが一般的です。高校入学以降の学歴にポイントを置いて、記入をしましょう。
転職者の場合
転職をするときには、職歴欄にもある程度記入する内容があります。このような場合には、高校を卒業した年から書くと学歴の欄をコンパクトにまとめられます。
アルバイトの面接の場合
フリーターや学生が、アルバイトの面接に履歴書を持っていくときは、中学校の卒業年から学歴を書きます。フリーターや学生は、職歴欄に書く内容が比較的限られているため、中学校の卒業から年号を書いてもスペースが足りなくなることは少ないでしょう。
「在学中」と「卒業見込み」ならどちらが正しいの?採用担当者は気にする?
就職活動中の学生は、学校に在籍している間に履歴書を書くケースが多いでしょう。現在の状況をどのように記載するべきかで悩むことがあるのが、このような学生の場合です。
「在学中」と「卒業見込み」のどちらで書いても問題はない
学生が学歴を書く際には、「在学中」や「卒業見込み」といった書き方があります。本当のところ、これらのいずれの書き方で書いても問題になることはありません。どちらの書き方であっても、採用、不採用に関係してくることはないでしょう。
卒業が間近であれば「卒業見込み」のほうがいい場合もある
数カ月後に卒業を控えているようなときには、「卒業見込み」のほうが適当かもしれません。「卒業見込み」と書くと、卒業単位に問題がなさそうだと思われる可能性が高く、「順調に卒業して就職できる学生」というイメージがより強くなります。入学して間もない時期に学歴を書く場合は、「在学中」のほうが自然でしょう。この場合、「卒業見込み」と記載すると、少し不自然な印象を与えることもあり得ます。
【イレギュラーなケースの学歴の書き方1】浪人や留年をした場合は?
少しイレギュラーな学歴を持っているときには、学歴欄の書き方にも工夫が必要になってきます。採用担当者にマイナスの印象を与えずに、事実を伝える方法を考えたいのが、例えば浪人や留年をしたケースです。
正しい卒業年度や入学年度を記入
浪人や留年をしても、卒業の年度や入学の年度は正確に書くことが必要です。卒業や入学した年を調べて、事実のとおりに年号を記載しましょう。浪人や留年の事実をたとえ隠したくても、事実と異なる内容を履歴書に書くのはご法度です。
浪人や留年のことには触れない
「浪人や留年をした」とわざわざと伝えなくても、卒業や入学の年号を見れば採用担当者も数年のずれがあることはわかります。浪人や留年をしていたことについては、学歴欄でもあえて触れる必要はないでしょう。面接などで聞かれたときに状況を説明すれば、とくに問題はありません。
【イレギュラーなケースの学歴の書き方2】休学をしている場合は?
病気などのやむを得ない事情で学校を休学した場合も、学歴欄の書き方に戸惑う可能性がでてきます。休学したときには、浪人や留年をした場合と同様にありのままの事実を学歴の欄に記入しましょう。
「○○高等学校 休学」と書く
例えば、高校を一時的に休学したときは、「○○高等学校 休学」のように、シンプルに事実を記載します。「病気のため」などの簡単な理由を書いておくと、「環境に適応することができなかったのでは」といった不安を採用担当者に抱かせずに済むでしょう。
他の学歴は休学期間に関係なく記入する
休学しているときでも、復学してからの学歴は通常通りに記入をします。休学期間を別枠に書いて説明する必要はありませんので、そのまま続けて以後の学歴を書いていきましょう。
【イレギュラーなケースの学歴の書き方3】中途退学をした場合は?
イレギュラーな学歴のケースとしては、中途退学をした場合も挙げられます。高校や大学などを中途退学したときには、次のような書き方で学歴欄を記入してみましょう。
「○○高等学校 中途退学」と記入する
該当する年号の欄に中途退学をした学校名を書き、右横に「中途退学」と記載します。中途退学の場合も、手短に「経済的な事情により」や「病気のため」などの理由を欄内に書いておいたほうがいいかもしれません。
面接のときや自己PR欄で中途退学をした理由を説明する
中途退学をしているときには、なぜ学校をやめたかをわかりやすく説明することが1つのポイントになるでしょう。履歴書を持参して面接を受ける場合は、面接の場で面接官に直接理由を述べましょう。書類選考があるときは、自己PR欄などで中途退学をした理由を説明する方法があります。勤務能力や仕事への姿勢に問題がないことを伝えられれば、マイナスの評価を受ける可能性は低くなります。
【イレギュラーなケースの学歴の書き方4】転校した場合はどうなる?
高校在学中などに転校をしたときには、学歴欄にも状況を書いておく必要があるでしょう。転校の場合も、学歴欄にはシンプルに事実を記入します。
入学した年度の欄に「○○高等学校 入学」と記入
学歴欄には、転校前に通っていた学校名を最初に書きます。まずは、該当する年度の欄に、通常通り「○○高等学校 入学」と記入しておきましょう。
下の欄に「××高等学校 転入学」と記入
「○○高等学校 入学」と書いた下の欄には、転校した先の学校名を記載し、右横に「転入学」と書き入れます。「××高等学校 転入学」と書いておけば、上の欄で書いた学校から転校した事実を説明できます。転校の場合はとくに理由を書く必要はありませんが、面接などで質問されたときには、「家族の転勤に伴って転居をした」などの事実を完結に述べましょう。
【イレギュラーなケースの学歴の書き方5】留学した場合はどう書くべき?
海外に留学をした場合は、どのくらいの期間、現地に滞在していたかが1つのポイントです。実際、滞在していた期間によっては学歴に該当しないケースもあります。その場合は、自己紹介欄や特記事項の欄などを利用して、海外滞在の経験を採用担当者にアピールできます。
1年未満のときには記入は不要
期間が1年に達しない留学は、学歴としては認められません。したがって、数カ月間の短期留学の経験があっても、学歴欄に記入する必要はないでしょう。高校や大学在学中に経験した短期の交換留学なども、学歴欄には書きません。
1年以上留学した場合は留学期間、国、学校名を記入
1年以上留学をしていたという場合は、学歴に該当します。留学していた期間や滞在していた国名、通学していた学校名などを欄内に記入しましょう。留学の学歴は、状況によっては1行にまとめて書くことも可能です。
【イレギュラーなケースの学歴の書き方6】学部や学科変更をした場合は?
大学の学部や学科を途中で変更した人も、少しイレギュラーな書き方をする必要がでてきます。ただ、このような場合も、転校のときとほぼ同じようなスタイルで記載できますので、取り立てて書き方が難しいといったことはありません。
入学した学部や学科を最初に書いておく
まずは、入学した時点の学部や学科を書いておきます。「大学名、学部名、学科名」を順に書き、右横に「入学」と記入しましょう。ここまでは、通常の学歴の書き方と同じです。
下の欄に変更した後の学部や学科名を記入
入学した時点の学部や学科を書いた下の欄には、変更した後の学部や学科名を別に書きます。この欄も、上の段と同様のスタイルで「大学名、学部名、学科名」と順に書いて、右横に「編入学」と書き入れます。同じ大学の中で別の学部や学科に移ったときにも、学校名を省略せずに大学の名前からしっかりと書くのがポイントです。レイアウトのバランスを考えながら、美しく仕上げましょう。
就活を成功させたいなら!学歴詐称は絶対にやめたほうがいい理由とは?
就活を成功させるうえでも絶対に避けたいのが、事実とは異なる学歴を記載する学歴詐称です。学歴詐称をした場合、いろいろな問題が浮上してきます。
卒業証明書で学歴が正しいかわかってしまうことがある
偽りの学歴で運よく採用になったとしても、その後に卒業証明書の提出などを求められたときには、すぐに履歴書に書いた学歴が事実でないことが発覚してしまいます。企業の中には、選考の途中や採用した後にあらためて卒業証明書の提出を求めるところもあります。卒業証明書は、本人が卒業した学校から発行してもらう書類です。卒業証明書には、偽造などができないような加工がほどこされていることもありますので、第3者が手に入れることはほぼ不可能です。
学歴詐称が発覚したら解雇される可能性が高い
学歴詐称をしていることが先方の会社に知られてしまった場合、採用された後でも解雇される可能性が高くなります。学歴詐称は、詐欺罪や文書偽造罪などに問われることもあるため、そのまま雇用されるケースは少ないと言えます。会社側から訴えられたり、罰を受けたりすることも考えられますので、軽い気持ちで学歴詐称をしてしまうのは避けましょう。
履歴書の年号は正しく記入しよう!間違えないようによく確認を!
面倒だと思っても、履歴書の年号や学歴は正しく記入をし、書き終わるまでミスをしないように気を付けることが大切です。年号は、その人の年齢や経歴にダイレクトに関わってきますので、不本意な間違いは避けなければなりません。年号の記入の際にミスをしないようにするには、次のような方法が役立つかもしれません。
- 年号の部分だけ、最後にもう一度確認をする
- 家族などに年号の部分をチェックしてもらう
履歴書を書いた後には内容をひととおり確認する方が多いですが、文字の表記などに気を取られていると、年号のチェックがおろそかになることもあります。ざっと文面をチェックした後に、あらためて年号の部分だけ確認をしておくとミスは少なくなるでしょう。また、信頼できる家族などに年号の部分を見てもらうのも1つの方法です。第3者に見てもらうと、自分では気がつかなかった問題点などを指摘してもらえることがありますので、より精度の高いチェックができます。履歴書の提出期限まで余り時間がないときでも、年号のチェックだけはしっかりと行っておきましょう。