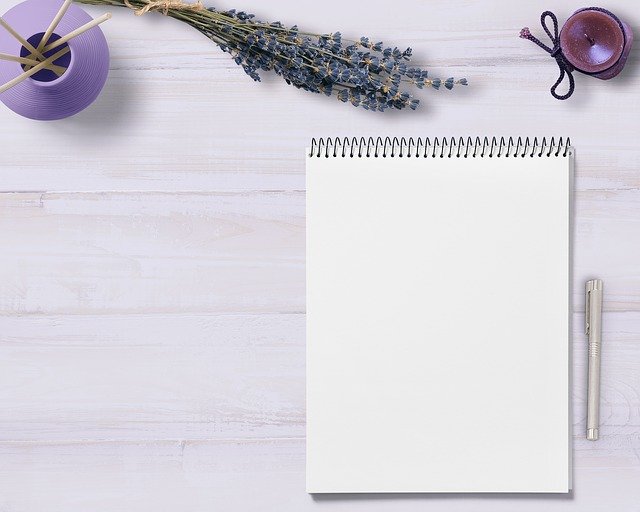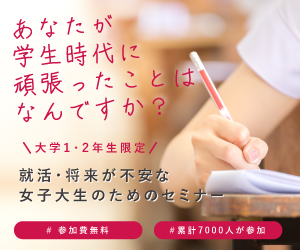時候の挨拶というのは、頭語の「拝啓」などに続く季節感を表す書き出しの言葉です。
時候の挨拶としては、学校関係で出す文書やビジネス文書、目上の方向けのお礼状の「漢語調」と、個人的な知人や親しい友達向けのカジュアルな「口語調」があります。
ここでは、6月の上旬、中旬、下旬にわけて、時候の挨拶の例文や結びの文、健康やコロナについての挨拶文、季節の話題についてご紹介します。
6月の時期
日本では現在新暦が使われていますが、季節の挨拶としては、二十四節気や旧暦が使われることがあります。
ここでは、どの二十四節気が6月なるか、旧暦のいつが6月になるかについてご紹介します。
どの二十四節気が6月なるかは、次のようになります。
忙種(ぼうしゅ)は、6月6日頃(その年によって違う)で、二十四節気の一つです。
現在のこの時期は、穀物の米や麦などの種をまくとされています。
夏至(げし)は、6月21日頃(その年によって違う)で、二十四節気の一つです。
この日は、1年の中で最も昼が長くなります。
旧暦のいつが6月になるかは、次のようになります。
- 旧暦の5月3日頃が新暦の2022年の6月1日
- 旧暦の6月1日が新暦の2022年の5月29日
- 旧暦の4月13日頃が新暦の2023年の6月1日
- 旧暦の6月1日が新暦の2023年の7月18日
- 旧暦の4月25日頃が新暦の2024年の6月1日
- 旧暦の6月1日が新暦の2024年の7月06日
書類、手紙、お礼状、メールで使う挨拶文の書き方、構成
学校関係で出す文書やビジネス文書、お礼状、個人的な手紙などを書くときは、基本的に前文、主文、末文、後付で構成します。
このような基本をベースにして、細かい要素を必要によって変えながら仕上げましょう。
前文は、頭語の「拝啓」など、時候の挨拶、相手の健康や安否を気遣う言葉、自分の近況やお礼などの順番に書きます。
主文は、本文になります。
末文は、結びの挨拶で、相手の繁栄や健康を祈る言葉、結語の「敬具」などの順番に書きます。
後付は、日付、署名、宛名の順番に書きます。
時候の挨拶の「漢語調」「口語調」は相手、シーンによって選ぶ
その時々の季節感を表した言葉が、時候の挨拶になります。
時候の挨拶としては、短く簡潔に表した「深緑の候」のような「漢語調」と、話し言葉で柔らかな「木々の緑が色濃くなる頃になりました」のような表現の「口語調」があります。
相手やシーンによって、「漢語調」と「口語調」は使いわけます。
一般的に、学校関係の文書やビジネス文書などでは、「漢語調」のかしこまった表現が使われることが多く、文書の格がアップします。
一方、より身近な「口語調」を使う方が、個人的な文書では多くあります。
また、ビジネスシーンでも、「口語調」を使って柔らかくすることもあります。
いずれにしても、おすすめはポジティブなものです。
ビジネスシーンの「漢語調」の6月の時候の挨拶
一般的に、かしこまった「漢語調」の時候の挨拶をビジネスシーンでは使います。
ここでは、目上の方へのメールや手紙でも使えるビジネスシーンの「漢語調」の6月の時候の挨拶についてご紹介します。
季節感が時候の挨拶は大切であるため、目安の時期ごとにご紹介します。
しかし、少しその年によってずれるときがあるため、季節感を実際に優先しながら選びましょう。
また、「○○の候」は、使うときに「○○のみぎり」「○○の折」に置き換えることもできます。
「青葉若葉(あおばわかば)の候」「桜桃(おうとう)の候」「深緑(しんりょく)の候」「梅雨(つゆ)の候」「向暑(こうしょ)の候」「梅雨寒(つゆざむ)の候」は 6月全般に使える
- 「青葉若葉の候」の意味は、青葉若葉の時期になりましたがということです。
- 「桜桃の候」の意味は、さくらんぼの季節になりましたがということです。
- 「深緑の候」の意味は、木々の緑が色濃くなる時期になりましたがということです。
梅雨のときであれば「梅雨の候」、暑いときであれば「向夏の候」、寒いときであれば「梅雨寒の候」なども、6月全般で使えます。
「青葉若葉の候」を使った例文としては、次のようなものなどがあります。
「青葉若葉の候、貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
「薄暑(はくしょ)の候」「麦秋(ばくしゅう)の候」「芒種(ぼうしゅ)の候」は6月上旬に使える
- 「薄暑の候」の意味は、暑さを少し感じる頃になりましたがということです。
- 「麦秋の候」の意味は、麦の穂が実って、収穫時期になりましたがということです。
「麦秋」は初夏の季語で、「麦秋至」は七十二候で5月31日頃~6月4日頃です。
- 「芒種の候」の意味は、穀類の種をまく頃になりましたがということです。
「芒種」は、6月5日頃~6月20日頃で、二十四節気の一つです。
「薄暑の候」を使った例文としては、次のようなものなどがあります。
「薄暑の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
「梅雨(つゆ)の候」「入梅(にゅうばい)の候」「長雨(ながあめ)の候」「黄梅(おうばい)の候」「霖雨(りんう)の候」は6月中旬~6月下旬に使える
- 「梅雨の候」の意味は、梅雨の時期になりましたがということです。
- 「入梅の候」の意味は、梅雨入りの時期になりましたがということです。
「入梅」は、6月11日頃以降、あるいは、実際の梅雨入りの頃に使います
- 「黄梅の候」の意味は、梅の実が色づく頃になりましたがということです。
- 「長雨の候」の意味は、梅雨の時期になりましたがということです。
- 「霖雨の候」の意味は、梅雨の時期になりましたがということです。
「梅雨の候」を使った例文としては、次のようなものなどがあります。
「梅雨の候、○○様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。」
「夏至(げし)の候」「向暑(こうしょ)の候」「短夜(みじかよ)の候」「小夏(こなつ)の候」「向夏(こうか)の候」は6月下旬に使える
- 「夏至の候」の意味は、夏至の頃になりましたがということです。
「夏至」は、6月21日頃~7月6日頃で、二十四節気の一つです。
- 「向暑の候」の意味は、暑い季節に向かっておりますがということです。
- 「短夜の候」の意味は、夏至を迎えて夜が短くなりましたがということです。
- 「小夏の候」の意味は、本格的な夏を前に暑い時期になりましたがということです。
- 「向夏の候」の意味は、夏に向かっておりますがということです。
「夏至の候」を使った例文としては、次のようなものなどがあります。
「夏至の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。」
ビジネスシーンの「口語調」の6月の結びの挨拶
趣旨や相手によって、結びの挨拶は変わります。
ここでは、ビジネスシーンの「口語調」の6月の結びの挨拶についてご紹介します。
今後もよろしくお願いしますというときの結びの挨拶
今後もよろしくお願いしますというときの結びの挨拶としては、次のようなものなどがあります。
- 「今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げます。」
- 「今後についても相変わらずご厚誼(こうぎ)を賜りますようお願い申し上げます。」
- 「ご高配を引き続き賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。」
- 「変わらぬご支援ご鞭撻をこれからも賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。」
相手の健康や繁栄を祈るときの結びの挨拶
相手の健康や繁栄を祈るときの結びの挨拶としては、次のようなものなどがあります。
- 「ますますの貴社のご発展を心よりお祈り申し上げます。」
- 「心より皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。」
- 「末筆ながら、衷心より一層のご隆盛をお祈り申し上げます。」
- 「心より皆様のご多祥をお祈り申し上げます。」
6月特有の結びの挨拶
6月特有の結びの挨拶としては、次のようなものなどがあります。
- 「鮮やかな青葉の色のこの季節、ますますのご活躍をお祈り申し上げます。」
- 「体長を長雨で崩されませんようにご留意ください。」
- 「梅雨寒の折、十分にご自愛をお願い申し上げます。」
- 「梅雨の候、十分に健康にはご留意なされ、さらにご活躍されますことをお祈り申し上げます。」
コロナ関係のときの結びの挨拶
- 「落ち着かない毎日がコロナ禍もあり続いております。十分にご自愛くださいますようお願い申し上げます。」
- 「梅雨寒の日もございますので、コロナ禍中、お体にくれぐれもご留意なされ、さらにご活躍されますことをお祈り申し上げます。」
個人的な「口語調」の6月の時候の挨拶
個人的な時候の挨拶のときは、書き出しはカジュアルな「口語調」の表現が好まれます。
ここでは、個人的な「口語調」の6月の時候の挨拶についてご紹介します。
「漢語調」の「○○の候」の言葉
「漢語調」の「○○の候」の言葉としては、次のようなものなどがあります。
- 「青葉若葉の時期になりましたが」
- 「桜桃の季節になりましたが」
- 「木々の緑が色濃い時期になりましたが」
- 「梅雨入りの時期になりましたが」
- 「梅の実が色づく頃になりましたが」
- 「梅雨の時期になりましたが」
- 「夏に向かっておりますが」
- 「夏至の頃になりましたが」
相手の健康や安否を気遣う言葉
相手の健康や安否を気遣う言葉としては、次のようなものなどがあります。
- 「衣がえの季節になりましたが、お変わりございませんか。」
- 「田植えも終わって、快い青田風の季節になりました。お健やかに皆様お過ごしのことと存じます。」
- 「今年も梅雨入りが気になる時期になりましたが、ご機嫌いかがでしょうか。」
- 「雨に紫陽花が映える季節になりましたが、皆様お元気でしょうか。」
- 「雨上がりのすがすがしい木々の緑の昨今ですが、いかがお過ごしでしょうか。」
- 「今朝は梅雨も中休みとなったのか、爽やかな青空が広がっております。皆様お元気でしょうか。」
- 「蛍が舞う時期になりました。皆様お元気でお過ごしのことと存じます。」
個人的な「口語調」の6月の結びの挨拶
カジュアルな表現が、個人的に使う結びの挨拶も好まれます。
挨拶の内容は相手によって考えてみましょう。
ここでは、個人的な「口語調」の6月の結びの挨拶についてご紹介します。
相手の嗜好、趣味に合わせたときの結びの挨拶
相手の嗜好、趣味に合わせたときの結びの挨拶としては、次のようなものなどがあります。
- 「梅雨が明けると、もうすぐ海開きで、心が今から弾みますね。」
- 「梅雨時のなぐさめに、せめておしゃれな傘で外を歩きたいものです。元気でお互いに過ごしましょう。」
- 「ホタルがそちらでは見られるそうで大変羨ましいです。ホタル狩りが愉しみですね。」
相手の体調を気遣うときの結びの挨拶
相手の体調を気遣うときの結びの挨拶としては、次のようなものなどがあります。
- 「梅雨明けが待たれる日々、皆様お元気でお過ごしください。」
- 「夏至を過ぎたといっても、梅雨寒のような日もございます。お身体にはくれぐれも気をつけてください。」
- 「体調を梅雨冷えに崩されませんように。」
- 「時節柄、体調を崩しませんようにお身体をおいといください。」
コロナ関係のときの結びの挨拶
コロナ関係のときの結びの挨拶としては、次のようなものなどがあります。
- 「時節柄、お目にかかることがなかなかできませんが、皆様のご多幸とご健勝を心よりお祈り申し上げます。」
- 「コロナ禍中、影響がお仕事にもあるかと存じます。お体に十分に気をつけてご活躍ください。」
- 「運動不足にテレワークでならないよう、お互いに注意しましょう。」
- 「コロナが収まりましたら、遊びにいらしてください。」
6月に使える季節の話題
ここでは、6月に使える季節の話題についてご紹介します。
季節の話題を使ってみると、季節感が出るでしょう。
6月の風物詩
6月の風物詩としては、梅雨、ジューンブライド、父の日、さくらんぼ狩り、夏至、あじさい、青梅、衣替え、山開きなどがあります。
旬の野菜
旬の野菜としては、たで、ししとうがらし、じゃがいも、紫蘇(しそ)、さやいんげん、アスパラガス、らっきょう、南瓜(かぼちゃ)などがあります。
旬の果物
旬の果物としては、梅、さくらんぼ、プラムなどがあります。
旬の海産物
旬の海産物としては、アオリイカ、甲烏賊(コウイカ)、鯣烏賊(スルメイカ)、雲丹(ウニ)、車海老(くるまえび)、毛蟹(けがに)、栄螺(さざえ)などがあります。