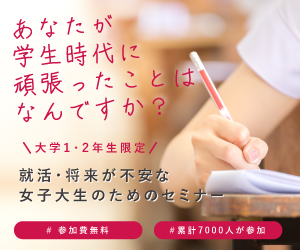「幸多からんことを」とは?
「幸多からんことを」というのは、いいできごとが多くありますように、幸せが多く訪れますように、ということです。
意味としては、相手の幸せを願うことがあります。
「幸多からんことを」の「多からん」の意味は、否定の意味の多くないということではありません。
「多からん」の「ん」の意味は否定ではなく、推量のことであり、このときのニュアンスは多かろうということです。
推量の意味で「む(ん)」の助動詞の使い方は古語のものであるため、「幸多からんことを」という表現も少し古く、堅いイメージになります。
なお、「幸多からんことを」は、「さちおおからんことを」と読みます。
「幸」は、訓読みが「さち、さいわ(い)、しあわ(せ)」で、音読みが「コウ」ですが、「幸多からんことを」のときは「さち」と読みます。
「幸多からんことを」の使い方とは?
ここでは、「幸多からんことを」の使い方についてご紹介します。
目上の方への「幸多からんことを」の使い方
目上の方に「幸多からんことを」は使わないようにしましょう。
文章として「幸多からんことを」のみでは完全ではないため、目上の方に使うのは失礼になります。
また、敬語の意味が「幸多からんことを」にはないため、そのまま使うのは適切ではありません。
「幸多からんことをお祈りします」「幸多からんことを願っています」
「幸多からんことを」は、「幸多からんことをお祈りします」「幸多からんことを願っています」の形で使います。
敬語表現としては、「お祈り申し上げます」「祈念いたします」などがあります。
「幸多からんことをお祈りします」を使った例文としては、次のようなものなどがあります。
- 「〇〇様に幸多からんことをお祈りします。」
「幸多からんことを」に対する返事には感謝の言葉を伝える
「幸多からんことを〜」に対する返事としては、感謝の言葉の「ありがとうございます」と伝えるといいでしょう。
手紙やメールのときは、「温かいお言葉をいただき恐縮しております」「お心遣いに感謝いたします」などのような返事もあります。
シーン別の「幸多からんことを」の使い方とは?
ここでは、シーン別の「幸多からんことを」の使い方についてご紹介します。
結婚式
相手の「幸せ」を願う代表的なシーンとしては、結婚式があるでしょう。
人生の中で幸せを最も感じると思う方も多くいるでしょうが、「幸多からんことを」という表現がぴったりのものです。
新郎新婦に贈るメッセージとして、「ご結婚を祝し、心からお慶びを申し上げるとともに、末永く幸多からんことをお祈り申し上げます。」などのように使います。
卒業式
人生の門出に相応しいシーンとしては、卒業式もあります。
新しい社会に飛び立とうとする卒業生に対するエールとして使います。
生徒たちの未来を願って、校長先生や担任の先生などが「皆さんの未来に幸多からんことをお祈りします。」などと使います。
入社式
入社式も、新しい会社に飛び込む門出のシーンです。
「幸多からんこと」は、新入社員に対して社長や先輩からのスピーチでよく使われます。
このときは、相手の幸せを単に願うよりは、仕事での相手の活躍を願うというようなニュアンスになります。
上長などからの「頑張れよ」という激励と捉えましょう。
「みんなの前途に、幸多からんことを心から祈っています。」などのように使います。
年賀状
友達同士の年賀状のときはカジュアルな表現の「あけおめ」や「ことよろ」などでもいいでしょうが、取引先や上長などに対する年賀状の文面には悩むでしょう。
「幸多からんことを」は、このようなかしこまったシーンの文章にもおすすめです。
思いを込めて、「新年も多くの幸せがあなたにありますように」などのように使うことができます。
「ご多幸をお祈り申し上げます。」と同じ意味で、「今年一年が、○○様にとって幸多からんことをお祈りします。」などのように使います。
「幸多からんことを」と同じような表現とは?
ここでは、「幸多からんことを」と同じような表現についてご紹介します。
「我と思わん者」
「幸多からんことを」と同じような表現としては、「我と思わん者」があります。
「我と思わん者」の意味は、自分は自信がある、優れていると思う者ということです。
使い方としては、「我と思わん者は、どんどんこの企画に応募して欲しい。」などのようなものがあります。
かっちゅうを着て戦国時代に戦った女性の名言として「我と思わん者は出だせたまえ」というものがあり、辞世の句として残っています。
「道遠からん」
「幸多からんことを」と同じような表現としては、「道遠からん」があります。
意味としては、肯定の「道は遠いだろう」ということになります。
なお、否定的な意味で「道遠からん」使うときは、「道遠からじ」や「道遠からず」になります。
「道遠からん」は、「遠から」という「遠し」の未然形に「む」という推量の助動詞が付いたものです。
口上の慣用句の「遠からん者は音にも聞け」は、戦場において武士が名乗りをあげるときに使うものです。
「遠からん者は音にも聞け」の意味は、遠くにいる者はこの声を聞けということです。
「幸多き人生であらんことを」
「幸多からんことを」と同じような表現としては、「幸多き人生であらんことを」があります。
このときの「あらん」は、「あらむ」がもともとで、「む」の意味は婉曲や推量のことです。
そのため、「幸多き人生であらんことを」の意味は、「幸多き人生であるような」「幸多き人生であるだろう」ということになります。
なお、「あらん」の否定形は、「ぬ」という「ず」の連体形を使った「あらぬ」になります。
「神の御加護があらんことを」
「幸多からんことを」と同じような表現としては、「神の御加護があらんことを」があります。
「神の御加護があらんことを」の意味は、神様の御加護がありますようにということになります。
もうちょっと砕けた意味としては、神様が見守って助けてくれますようにということになります。
このときの「あらん」は、「幸多き人生であらんことを」の「あらん」と同じように、「あらむ」で「ん」に「む」が変わったものです。
「む」は、婉曲の「~としたら」や推量の「~だろう」という意味の助動詞です。