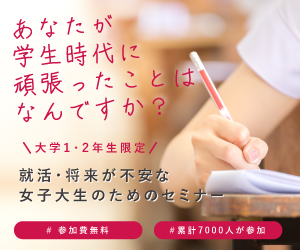「焦燥感」の意味とは?
「焦燥感」の意味は、思う通りにならなくてイライラする気持ち、目的が達成しないで焦る気持ちです。
ほとんど「焦燥」も意味が同じですが、「感」を「焦燥」に付けることによって、一言で心理状態の「焦る気持ちを感じている」ということを表現することができます。
「焦燥」は「焦躁」とも古くは書きましたが、現在は一般的に「焦燥」です。
「焦」の意味は、考えているようにならないことなどによってイライラするということです。
「焦す」というときの意味は、焼けてこげた状態にするということにプラスして、悩ますということもあります。
「燥」の意味は、「苛立つ」ということがあります。
「焦燥」は、「心を焦げるほど悩ます、イライラする」という気持ちと、思うようにならない不快感を表現します。
「焦燥感」の使い方とは?
人の心情に「焦燥感」は使われます。
苛立ちを期限内にやるべき仕事などが終了しない焦りから覚えたりするときに、「焦燥感」は使います。 「焦燥感」はちょっと焦ったときなどは使いません。
例えば、集まる時間を間違って「遅れるのではないかということで焦った」などというような気持ちは、「焦燥感」ではありません。
「焦燥感」を使うのは、じっとしていられないくらい落ち着かない苛立ちや焦りを覚えたときです。
使い方としては、「焦燥感です」というようなものはあまりしません。
「焦燥感」の主な使い方としては、次のようなものがあります。
- 焦燥感に苛まれる、駆られる
- 焦燥感を抑える、煽る
- 焦燥感が募る
「焦燥感」を使った例文としては、次のようなものがあります。
- 「頼まれた仕事が上手く期限内に終わるかわからないため、焦燥感に駆られる。」
- 「どうしようもない焦燥感に苛まれ、十分に睡眠できない。」
- 「なかなか明日の会議の資料ができなく焦燥感のみが募る。」
- 「周他の人が結婚していく中において、焦燥感を抑えて業務に励む。」
「焦燥感」を感じる要因とは?
ほとんどの人は「焦燥感」を感じたことがあるのではないでしょうか。
人にとって「焦燥感」は身近な一つの感情です。
しかし、焦って常にイライラしていれば、負担が心身ともにかかるでしょう。
では、人は「焦燥感」をどうして感じるのでしょうか?
「焦燥感」を感じる要因はいろいろです。
置かれた状況や個人の性格によって、「焦燥感」は違っています。
「焦燥感」を感じる要因は、結果を仕事で出せない、上手く恋愛がいかない、目標が人生に見いだせないなどがありますが、ほとんどは自律神経がストレスによってアンバランスになることが挙げられます。
交感神経がストレスを感じて優位になれば、緊張状態に常になって落ち着きません。
そのため、不安や焦りをさらに感じやすくなって、「焦燥感」を常に感じるようになります。
「焦燥感」を無くすには、副交感神経を優位にしてリラックスする必要があります。
「焦燥感」を無くす方法とは?
「焦燥感」を無くすためには、リラックスするために自律神経のアンバランスを整える必要があります。
人は基本的に「焦燥感」を感じますが、感じにくい人と感じやすい人が性格によっています。「焦燥感」を感じやすいのは、次のような人です。
- 完璧主義者
- 真面目
- 几帳面
- 比較する癖がある
- 世間体を気にする
- 弱みを他の人に見せたくない
- 心配症
- 自分のことが嫌い
「焦燥感」を感じやすい人は、「焦燥感」を可能な限り感じにくいように努力しましょう。
ここでは、「焦燥感」を無くす方法についてご紹介します。
他の人と比較しない
「焦燥感」を感じやすい人のほとんどは、自分と他の人を比較しています。
例えば、次のように他の人と比較することによって、自分の歩みが遅いことを嘆き、焦りを感じます。
- 「友達は全て結婚しているが、自分は恋人さえもいない。」
- 「ほとんどの同僚が出世しているが、自分のみどうしても出世できない。」
また、他の人と比較するのみでなく、現在の自分と理想の自分を比較しているときもあります。
「もっとできるはずである」「もっと輝きたい」と考えるほど、理想の自分とかけ離れた現在の自分がわかって、「焦燥感」を感じるようになります。
現代はネットが普及しているため、簡単にSNSなどで自分と他の人を比較することができます。
しかし、そこに映し出された全てのものが現実であるという確かな証拠はありません。
他の人と比較するのは止めましょう。
「焦燥感」の類義語とは?
ここでは、「焦燥感」の類義語についてご紹介します。
「圧迫感」
「圧迫感」というのは、圧力の押さえつけなどがかかっている感じ、あるいは、威圧的に迫ってくる感じです。
「圧迫感」という言葉は、「焦燥感」と同じように、それほどいい感覚や感情を意味するものではありません。
しかし、「圧迫感」のときは、苛立ちや焦りよりも、窮屈な感じや押さえつけられるような息苦しさを意味しています。
「切迫感」
「焦燥感」というのは、さまざまなことが差し迫って緊張していたり、逃げ場がなくて追い詰められた感情であったりする心情を表現します。
「切迫感」は、大きく見れば、「焦燥感」と同じように「焦り」を意味するものです。
しかし、「焦燥感」のように、「焦り」にプラスして「苛立ち」を感じるよりも、危機が迫る感じや「焦り」から来る「緊張感」というような意味合いがより強いともいえます。
「焦燥感」の英語表現とは?
「frustration」が、「焦燥感」の英語表現の形容詞になります。
意味合いとしては、思い通りにいかなくてイライラする気持ちが強いものです。
心配から起きる焦りも含まれる「焦燥感」の英語表現としては、「不機嫌」という意味の「fretfulness」があります。
うつ病と「焦燥感」の関係とは?
では、うつ病と「焦燥感」はどのような関係があるのでしょうか?
「焦燥感」は、うつ病の一つの症状になります。
うつ病の症状としては、落ち着かなくて歩き回ったりするだけでなく、話を急き立てられるように継続するというようなものも現れます。
しかし、口数が多くなっても、ほとんど話がかみ合わないときがあります。
「焦燥感」としてうつ病のときに感じるものは、お金に対する心配、将来に対する心配、家族に対する心配などいろいろな不安感があります。
うつ病は、ストレスがメンタル的にあるだけでなく、ストレスが身体的な要因で発症するときがあります。
よく要因がわからない「焦燥感」が感じられるときが継続すれば、ストレスがないか確認してみましょう。なお、ネットなどではうつ病が簡単に確認できるようなサイトが多くあります。
うつ病は対処を早く行うほど、完治する可能性が大きくなるため、早めにクリニックを受診するようにしましょう。