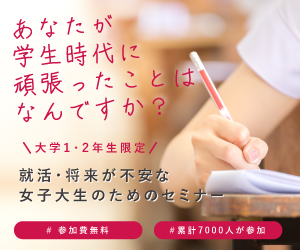「動機づけ」は、モチベーションともいわれており、人を行動する気持ちにさせて、積極的な目標を達成しようという感情も出てくることで、この行動を保たせる機能があります。
「動機づけ」としては、「外発的動機づけ」と「内発的動機づけ」があります。
「外発的動機づけ」は人が評価や報酬などのために行動することで、「内発的動機づけ」はやりたいので行動することです。
「外発的動機づけ」の時は、行動したことによって獲得できる理由、あるいは強制や義務というような理由から行動します。
一方、「内発的動機づけ」の時は、本人の興味や関心、意欲によって行動します。
「動機づけ」は、心理学の一つのテーマとして取り扱われ、モチベーション理論というどのように人が「動機づけ」られてやる気がアップするかについて研究するものに展開します。
初めの時期のモチベーション理論は、ハーズバーグの衛星理論、マズローの欲求階層説、マクレガーのX理論Y理論などに1950年代に発展しました。
この3つのモチベーション理論が、現代のモチベーション理論のベースになっています。
モチベーション理論の多くはアメリカの研究者によるものであるため、理論としてはアメリカ人に適したものが多くあります。
しかし、日本においても、「動機づけ」はやる気をアップするための方法としてスポーツや学習、社員教育などで利用されています。
「内発的動機づけ」がやる気を保つためには大切
「動機づけ」としては、「外発的動機づけ」と「内発的動機づけ」があります。
「外発的動機づけ」というのは、外部の人からの誘因によって「動機づけ」するものです。
例えば、ビジネスシーンでの「外発的動機づけ」は、金銭的な給料のアップや賞与などの褒美、花形部署への異動や昇進、充実した福利厚生などがあげられます。
「外発的動機づけ」は、このような見返りを要求してやる気を出すものです。
短期的には「外発的動機づけ」の効果がありますが、限界が物理的にあるというデメリットもあるため長続きしません。
例えば、全ての社員を課長に昇進させることはできないでしょう。
一方、「内発的動機づけ」というのは、自分の内面から湧いてくるものです。
目標を自分で決めるので、成長の実感や達成感を得やすくなります。
限界は物理的になく、無制限に自分の考え方によって「動機づけ」ができます。
そのため、やる気を保つためには、「内発的動機づけ」が大切であるとされています。
行動イノベーションの専門家は、「内発的動機づけ」を上手く利用してやる気を導き出すためには、適切な「意味づけ」を仕事に対して行うといいといっています。
「一般的な人生の意味はない。人生の意味は自分自身で与えるものだ」ということを、オーストリアのアドラーもいっています。
「確かに現在の仕事は厳しいが、次にこの経験が生かせるはずである」あるいは「この職場に自分は求められている人材である」などというように、自分で現在の職場、仕事の意味を決めることが大切です。
行動イノベーションの専門家は、「上手くいつもいっている人は、意味づけが例外なく上手である。自分が置かれている状態が変わるごとに、意味を新しく見出し、自然にやる気が湧いてくる状態を作っている。」といっています。
「外発的動機づけ」に頼りすぎていると、気に入らない部署に異動した時にやる気が全く無くなったというようなことになるでしょう。
上長がやる気がない部下に「もっと頑張れ」というようなシーンをよく目にするのではないでしょうか。
しかし、部下のやる気を導き出すためには、このような言葉は有効とはいえないでしょう。
アドラー派の心理カウンセラーの人によれば、「もっと頑張れ」といわれた人は現在のままでは駄目であるといわれたように思うそうです。
そして、これによってやる気が余計になくなるそうです。
どのようなことに「動機づけ」されるかは個人によって違う
「動機づけ」と一言でいっても、どのようなことによって「動機づけ」されるかというのは、個人によって違っています。
「動機づけ」が同じようなものでも、ほとんど反応しないような人や強く反応する人がいます。
では、「動機づけ」が同じでもどうしてこのように違いがあるのでしょうか?
例えば、どうして人は歯を磨くかについてご紹介しましょう。
まず、虫歯になるのを防ぎたいという人は、虫歯になるというトラブルを避けることが「動機づけ」になっており、問題回避型とこのようなタイプの人をいいます。
問題回避型の人は、避けるべきことや解決すべきトラブルがあれば、やる気がアップするとされています。
一方、美しくきれいに歯を見せたいという人は、美しい歯になりたいたいということが「動機づけ」になっており、目的志向型とこのようなタイプの人をいいます。
目的志向型の人は、取得したり、所有したり、達成したり、到達したりすることによってやる気がアップするとされています。
このように、同じような行動であっても、どのようなことに「動機づけ」されるかは、個人によって違ってきます。
そして、「動機づけ」としては個人に応じた方法が必要になってきます。
そのため、個別に従業員のやる気を導き出すような時には、何によって従業員が「動機づけ」されるかを掴んだうえで、「動機づけ」を従業員のタイプに応じた方法によって行う必要があります。
「外発的動機付け」とは?
「外発的動機付け」については、たぶん子供の頃に多くの人が経験したことがあるのではないでしょうか。
例えば、「今度の試験でいい点数をとれば新しいゲーム機を買おう」あるいは「お手伝いをすればお小遣いをあげる」というようなものです。
このように、「外発的動機付け」は、報酬によって行動を子供に起こさせようとするものです。
そのため、「外発的動機付け」は、「動機づけ」を外部からの誘因によって行うものです。
当然ですが、「外発的動機付け」は、親子関係以外に、大人になってからも多くあります。
例えば、評価が会社の中で上がると、昇格したり、昇給したり、ボーナスが増額したりするものです。
また、勤務態度が良くなければ、減給したり、降格したりするものです。
サラリーマンであれば、当然ですが評価基準も実際には「外発的動機付け」になります。
「外発的動機付け」は、目の前に明確な報酬があるので、これが欲しい人には抜群の効果があることがメリットでしょう。
例えば、小学校の頃に、家で友達とゲームをするためにかけ算の九九を記憶する必要があり、ゲームをやるために九九を必死になって記憶したことがあるのではないでしょうか。
「外発的動機付け」は、やる気を効果的に導き出すためには有効です。