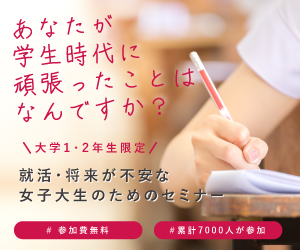「ダンピング」の意味とは?
「ダンピング」は、「適切でない価格で販売することによってマーケットを混乱させること」という意味です。
「ダンピング」は、いろいろな業界や国で起きたときがあります。
「不当廉売」ともいわれており、戦略的に競合している相手を苦しめる安売りです。
しかし、「ダンピング」に関する具体的な過去の事例や、「ダンピング」に関する熟語が正しくわかっている方は多くないのではないでしょうか。
「ダンピング」について理解を深めましょう。
「ダンピング」を使い方とは?
ここでは、「ダンピング」の使い方として、いろいろな熟語についてご紹介します。
「ソーシャルダンピング」
「ソーシャルダンピング」というのは、国外に国や社会的規模で輸出を不当に安く行うことで、「社会的投売」といわれています。
1930年代に日本は雑貨や綿布の輸出が急激に多くなったことついて、「ソーシャルダンピング」を欧米諸国から指摘されました。
「ソーシャルダンピング」は、輸出量が新興国によって拡大したことについて先進国が指摘するときが多くあります。
しかし、日本も輸出量が第二次大戦前に多くなったときに「ソーシャルダンピング」を指摘されました。
「ダンピング受注」
「ダンピング受注」は、公共事業に多くありますが、大幅に予定した価格よりも安く受注することです。
日本の建設業界においては、「ダンピング受注」が1970年代頃から指摘されていました。
「ダンピング受注」は、工事が手抜きされたり、建物や建設現場の安全が悪くなったりすることがあります。
そのため、受注するときの予定価格の66.6%〜85%を目途にして、この目途を下回るときは「低入札価格調査」が行われます。
「ダンピング輸出」
「ダンピング輸出」というのは、不当に安く輸出することです。
「ダンピング輸出」であると認められると、関税の賦課が世界貿易機関(WTO)の権限で認められます。
「ダンピング輸出」の目的は海外におけるシェアを拡げるためで、国外価格を国内価格よりも非常に安くしています。
継続的な商品の輸入によって、不利益が国内の産業にあることが予想されて「ダンピング輸出」が認められると、ダンピング関税の賦課が世界貿易機関の権限で認められます。
「ダンピング販売」
「ダンピング販売」は、非常に安く正当な理由なしで販売することで、公正取引委員会や独占禁止法で禁止されています。
「ダンピング販売」は、会社の在庫を大量に処理するなどのために実施されるときがあります。
しかし、独占禁止法では、サービスや商品の価格を正当な理由がなくて非常に安く販売することが禁止されています。
「ダンピング競争」
「ダンピング競争」というのは、皮肉交じりに会社間による安売り競争をいうものです。
日本では、商品を不当に安く販売することは独占禁止法によって禁止されていますが、公正なマーケットメカニズムに従った競争の枠内で価格を安くすることは認められています。
しかし、商品が成熟したマーケットでは会社同士の商品レベルやコスト構造は同じようなものであるため、よく「ダンピング競争」が起きるようになります。
具体的な「ダンピング」の事例とは?
ここでは、過去の具体的な「ダンピング」の事例についてご紹介します。
なお、事例はオーストラリアに対する日本の「ダンピング」に関するものです。
「ダンピング」では、関税が対応策として賦課されていることに着目しておきましょう。
日本は、高温で圧延した鉄鋼を板に加工した「熱間圧延鋼板」を盛んに輸出していますが、不当に安く輸出していたため、「アンチダンピング関税」の措置をオーストラリアから受けていました。
「アンチダンピング関税」というのは、特別に「ダンピング」に対して賦課する関税です。
オーストラリア政府が2017年に調べた結果、この「アンチダンピング関税」は継続的な将来の「ダンピング」の影響が少ないということで撤廃されました。
「ダンピング」のメリット・デメリットとは?
会社は、急激なマーケットの需要の縮小などによって、在庫を大量に抱えるときがあります。
「ダンピング」は、会社が抱えた在庫を大量に処分する方法として使われるときもあります。
「ダンピング」のメリットとしては、次のようなものがあります。
- 在庫を処分することによって損失が軽くなる
- 「ダンピング」で安く売ることを継続することによって、需要が回復することがある
一方、「ダンピング」のデメリットとしては、次のようなものがあります。
- 資本力が強い会社が弱い会社の事業を妨害する
- 健全なマーケット競争が妨害される
- 負担がユーザーの生活にかかる可能性が大きい
「ダンピング」についての法律とは?
法律的にも「ダンピング」は良くありません。
ここでは、「ダンピング」についての法律についてご紹介します。
「独占禁止法」
「独占禁止法」は、自由で公正なマーケット競争を促進し、事業者自身の創意工夫によって事業活動が自由にできるようにするための法律です。
「独占禁止法」によってユーザーの利益が保護されて、自由にニーズに合う商品が選択しやすくなります。
次の項目に該当する「ダンピング」は、独占禁止法に違反します。
- 儲けを無視した過剰な安売りを、正当な理由がなくて継続する
- 悪い影響を別の事業者に与え、事業活動が難しくなっている
- 「ダンピング」している事業者のマーケットでの規模が大きい、地位が高い
違反したときは、次のような罰則があります。
- 「排除措置命令」が「ダンピング」を止めるように出される
- 過去10年以内にも「ダンピング」を行って行政処分されたなど一定の条件をクリヤーしていたときは、課徴金納付が命令される
販売する価格が需要と供給の関係で下がっているときや季節商品やキズ物の処分などは、「正当な理由があるダンピング」ということで違法ではありません。
「国際経済法」
国際的な経済関係を規制する法律が、「国際経済法」です。
なお、この法律についての考え方は、まだ決まっていないようです。
次の項目に該当するときは、「国際経済法」に違反します。
世界貿易機関の協定で認められている報復措置が、特別にとられることがあります。
- 輸出する国の販売価格よりも非常に安く商品が輸入される
- 輸入する国の産業が被害を安い輸入品によって受けている
報復措置としては、次のようなものがあります。
- アンチダンピング関税
関税を適正価格と「ダンピング」している価格の差額以下の税率で掛ける関税措置
- 相殺関税措置
特定の補助金を政府から受給して生産した安い輸入品について、関税をこの補助金の影響を相殺するために掛ける関税措置