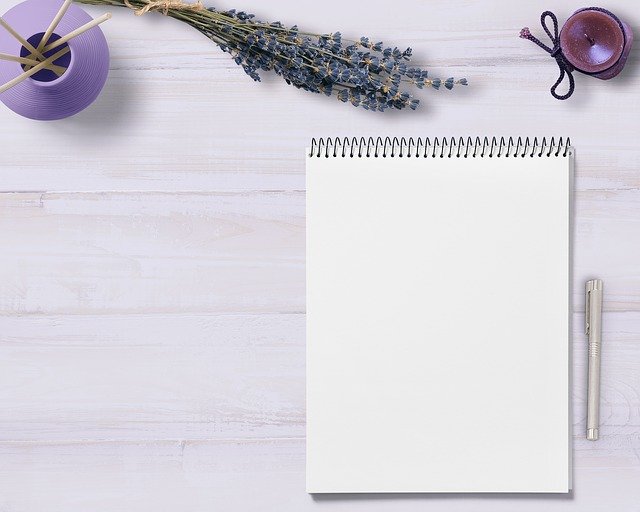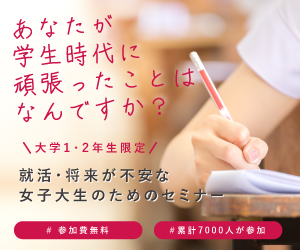時候の挨拶というのは、頭語の「拝啓」などに続く季節感を表す書き出しの言葉です。
時候の挨拶としては、学校関係で出す文書やビジネス文書、目上の方向けのお礼状の「漢語調」と、個人的な知人や親しい友達向けのカジュアルな「口語調」があります。
ここでは、2月の上旬、中旬、下旬にわけて、時候の挨拶の例文や結びの文、健康やコロナについての挨拶文、季節の話題についてご紹介します。
2月の時期
日本では現在新暦が使われていますが、季節の挨拶としては、二十四節気や旧暦が使われることがあります。
ここでは、どの二十四節気が2月なるか、旧暦のいつが2月になるかについてご紹介します。
どの二十四節気が2月なるかは、次のようになります。
立春(りっしゅん)は、2月4日頃(その年によって違う)です。
春はこの頃から始まるとされています。
雨水(うすい)は、2月19日頃(その年によって違う)です。
草木の芽が出始めて水がぬるみ始めるのは、この頃からとされています。
旧暦のいつが2月になるかは、次のようになります。
- 旧暦の1月1日頃が新暦の2022年の2月1日
- 旧暦の2月1日が新暦の2022年の3月3日
- 旧暦の1月11日頃が新暦の2023年の2月1日
- 旧暦の2月1日が新暦の2023年の2月20日
- 旧暦の12月22日頃が新暦の2024年の2月1日
- 旧暦の2月1日が新暦の2024年の3月10日
書類、手紙、お礼状、メールで使う挨拶文の書き方、構成
学校関係で出す文書やビジネス文書、お礼状、個人的な手紙などを書くときは、基本的に前文、主文、末文、後付で構成します。
このような基本をベースにして、細かい要素を必要によって変えながら仕上げましょう。
前文は、頭語の「拝啓」など、時候の挨拶、相手の健康や安否を気遣う言葉、自分の近況やお礼などの順番に書きます。
主文は、本文になります。
末文は、結びの挨拶で、相手の繁栄や健康を祈る言葉、結語の「敬具」などの順番に書きます。
後付は、日付、署名、宛名の順番に書きます。
時候の挨拶の「漢語調」「口語調」は相手、シーンによって選ぶ
その時々の季節感を表した言葉が、時候の挨拶になります。
時候の挨拶としては、短く簡潔に表した「向春の候」のような「漢語調」と、話し言葉で柔らかな「春が訪れる頃になりました」のような表現の「口語調」があります。
相手やシーンによって、「漢語調」と「口語調」は使いわけます。
一般的に、学校関係の文書やビジネス文書などでは、「漢語調」のかしこまった表現が使われることが多く、文書の格がアップします。
一方、より身近な「口語調」を使う方が、個人的な文書では多くあります。
また、ビジネスシーンでも、「口語調」を使って柔らかくすることもあります。
いずれにしても、おすすめはポジティブなものです。
ビジネスシーンの「漢語調」の2月の時候の挨拶
一般的に、かしこまった「漢語調」の時候の挨拶をビジネスシーンでは使います。
ここでは、目上の方へのメールや手紙でも使えるビジネスシーンの「漢語調」の2月の時候の挨拶についてご紹介します。
季節感が時候の挨拶は大切であるため、目安の時期ごとにご紹介します。
しかし、少しその年によってずれるときがあるため、季節感を実際に優先しながら選びましょう。
また、「○○の候」は、使うときに「○○のみぎり」「○○の折」に置き換えることもできます。
「梅花(ばいか)の候」「向春(こうしゅん)の候」「梅鴬(ばいおう)の候」は2月全般に使える
- 「梅花の候」の意味は、梅の花が咲く頃になりましたということです。
- 「向春の候」の意味は、春が訪れる頃になりましたということです。
- 「梅鴬の候」の意味は、梅がほころび、鶯の鳴く頃になりましたということです。
「梅花の候」を使った例文としては、次のようなものなどがあります。
- 「梅花の候、ますます貴社ご繁栄のこととお慶び申し上げます。」
「晩冬(ばんとう)の候」「暮冬(ぼとう)の候」は1月下旬~2月初めに使える
「晩冬の候」の意味は、冬も終わりになりましたということです。
「晩冬」は、1月5日頃~2月3日頃で、二十四節気の小寒~大寒をいいます。
「暮冬の候」の意味は、冬も終わる頃になりましたということです。
冬は、暦の上では2月3日頃の立春の前日までになります。
「余寒(よかん)の候」「立春(りっしゅん)の候」「春寒(しゅんかん)の候」「残寒(ざんかん)の候」は2月上旬~2月中旬に使える
「余寒の候」の意味は、立春を過ぎましたが、寒い日がまだまだ続きますということです。
「余寒」は、2月4日頃の立春以降の寒さをいいます。
「立春の候」の意味は、春に暦の上ではなりましたということです。
「立春」は、2月4日頃~2月18日頃で、二十四節気の一つです。
「春寒の候」の意味は、立春を過ぎても寒さがぶり返す頃ですということです。
「残寒の候」の意味は、寒の時期を過ぎましたが、寒い日がまだ続きますということです。
「残寒」は、寒の時期(1月5日頃~2月3日頃の二十四節気の小寒~大寒)を過ぎても寒さが残ることをいいます。
「余寒の候」を使った例文としては、次のようなものなどがあります。
- 「余寒の候、○○様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。」
「残雪(ざんせつ)の候」「雨水(うすい)の候」は2月下旬に使える
「残雪の候」の意味は、消え残る雪がまだ見られる時期ですということです。
「雨水の候」の意味は、雪から雨に変わって、氷や雪が解けだす頃になりましたということです。
「雨水」は、2月19日頃~3月5日頃で、二十四節気の一つです。
「残雪の候」を使った例文としては、次のようなものなどがあります。
- 「残雪の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
ビジネスシーンの「口語調」の2月の結びの挨拶
趣旨や相手によって、結びの挨拶は変わります。
ここでは、ビジネスシーンの「口語調」の2月の結びの挨拶についてご紹介します。
今後もよろしくお願いしますというときの結びの挨拶
今後もよろしくお願いしますというときの結びの挨拶としては、次のようなものなどがあります。
- 「今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げます。」
- 「今後についても相変わらずご厚誼(こうぎ)を賜りますようお願い申し上げます。」
- 「ご高配を引き続き賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。」
- 「変わらぬご支援ご鞭撻をこれからも賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。」
相手の健康や繁栄を祈るときの結びの挨拶
相手の健康や繁栄を祈るときの結びの挨拶としては、次のようなものなどがあります。
- 「ますますの貴社のご発展を心よりお祈り申し上げます。」
- 「心より皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。」
- 「末筆ながら、衷心より一層のご隆盛をお祈り申し上げます。」
- 「心より皆様のご多祥をお祈り申し上げます。」
2月特有の結びの挨拶
2月特有の結びの挨拶としては、次のようなものなどがあります。
- 「向春の候、ますますのご活躍とご健勝をお祈りいたします。」
- 「余寒厳しき折、ご自愛をお願い申し上げます。」
- 「三寒四温の時節柄、体調管理には何卒ご留意ください。」
- 「春寒の候、十分に健康にはご留意なされ、さらにご活躍されますことをお祈り申し上げます。」
コロナ関係のときの結びの挨拶
- 「落ち着かない毎日がコロナもあり続いております。十分にご自愛くださいますようお願い申し上げます。」
- 「コロナ禍中、寒い日もまだ続きますが、お体にくれぐれもご留意なされ、ご活躍されますことをお祈り申し上げます。」
個人的な「口語調」の2月の時候の挨拶
個人的な時候の挨拶のときは、書き出しはカジュアルな「口語調」の表現が好まれます。
ここでは、個人的な「口語調」の2月の時候の挨拶についてご紹介します。
「漢語調」の「○○の候」の言葉
「漢語調」の「○○の候」の言葉としては、次のようなものなどがあります。
- 「春が訪れる頃になりました。」
- 「春が近づいておりますが、寒い日がまだ続いております。」
- 「春に暦の上ではなりました。」
- 「春の訪れを寒さのなかにも感じる頃になりました。」
- 「梅がほころび、鶯の鳴く頃になりました。」
- 「消え残る雪がまだ見られるこの時期、」
- 「梅の便りも耳にする今日この頃、」
- 「雪から雨に変わり、氷や雪の解けだす頃になりました。」
- 「梅のつぼみもふくらみ、春を陽だまりに感じる頃になりました。」
相手の健康や安否を気遣う言葉
相手の健康や安否を気遣う言葉としては、次のようなものなどがあります。
- 「節分が終わり、春の到来をいよいよ待ちわびる頃になりましたが、皆様お変わりございませんか。」
- 「ようやく蕗の薹が顔を出す時期になりました。その後お変わりございませんでしょうか。」
- 「水ぬるむ季節になりましたが、風邪などお召しになっておられませんか。」
- 「春の訪れを日差しに感じる季節になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。」
- 「日脚が少しづつ伸びてくる頃になりました。お健やかに皆様お過ごしでしょうか。」
- 「今日この頃は梅の蕾がふくらみ、春の訪れが待ち遠しいですが、お元気でお過ごしでしょうか。」
- 「早春の息吹が寒気の中にも感じられる頃になりましたが、ご機嫌いかがですか。」
- 「春一番が先日吹いて、春の訪れが感じられるようになりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。」
- 「梅の蕾が、冷たい空気のなかでもほころび始めました。ずいぶんご無沙汰しておりますが、お元気でご活躍のことと存じます。」
- 「雨水を迎え、雛人形を我が家では出しました。お健やかに皆様お過ごしでしょうか。」
「雨水」は、2月19日頃~3月5日頃で、二十四節気の一つです。
個人的な「口語調」の2月の結びの挨拶
カジュアルな表現が、個人的に使う結びの挨拶も好まれます。
挨拶の内容は相手によって考えてみましょう。
ここでは、個人的な「口語調」の2月の結びの挨拶についてご紹介します。
相手の嗜好、趣味に合わせたときの結びの挨拶
相手の嗜好、趣味に合わせたときの結びの挨拶としては、次のようなものなどがあります。
- 「暖かくなりましたら、こちらにもどうぞお出かけください。」
- 「梅の名所がこちらにはございます。ご家族でぜひ遊びにいらしてください。」
- 「庭の金柑(きんかん)で今年も甘露煮(かんろに)を作りました。喉にも良いため、食べにぜひ来てくださいね。」
相手の体調を気遣うときの結びの挨拶
相手の体調を気遣うときの結びの挨拶としては、次のようなものなどがあります。
- 「時節柄、体調を悪くしませんよう、お身体をおいといください。」
- 「雪がなくなるまでそちらも大変かと存じます。皆様、健やかにどうかお過ごしください。」
- 「花粉症が早くも猛威をふるっているようです。時節柄、十分にご自愛下さい。」
- 「朝夕の寒さには、向春といえども油断なさいませんように。」
コロナ関係のときの結びの挨拶
コロナ関係のときの結びの挨拶としては、次のようなものなどがあります。
- 「コロナ禍もございますので、余寒の折、十分にお体にはご留意ください。」
- 「時節柄、お目にかかることがなかなかできませんが、皆様のご多幸とご健勝を心よりお祈り申し上げます。」
- 「コロナ禍中、影響がお仕事にもあるかと存じます。残寒の候、お体に十分に気をつけてご活躍ください。」
- 「運動不足にテレワークでならないよう、お互いに注意しましょう。」
- 「残寒にくわえてコロナもございますので、十分にご自愛くださいませ。」
- 「時節柄、思うようになかなか会うことができませんが、おしゃべりをオンラインでするのも大歓迎です。元気でお互いに頑張りましょう。」
2月に使える季節の話題
ここでは、2月に使える季節の話題についてご紹介します。
季節の話題を使ってみると、季節感が出るでしょう。
2月の風物詩
2月の風物詩としては、豆まき、節分、確定申告、梅見、恵方巻き、入試、バレンタイン、立春などがあります。
旬の野菜
旬の野菜としては、小松菜、チンゲンサイ、独活 (うど)、ふきのとう、菜の花などがあります。
旬の果物
旬の果物としては、りんご、八朔などがあります。
旬の海産物
旬の海産物としては、鱈(たら)、金糸魚(いとより)、白魚(しらうお)、公魚(わかさぎ)、笠子(かさご)、鮪(まぐろ)などがあります。