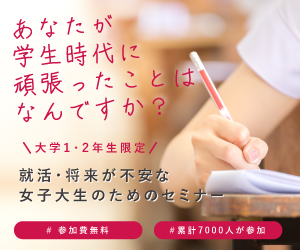動機付け理論とは?
動機付け理論というのは、行動科学理論で、フレデリック・ハーズバーグという臨床心理学者によって提唱されたものです。
動機付けは、目標に向けた行動を促進・保持するためのプロセスまたは機能で、モチベーションのことです。
フレデリック・ハーズバーグの研究によって、仕事の動機付けに不快感をもたらす要因と満足感をもたらす要因は種類が全く違うものであることがわかりました。
これが動機付け理論における外発的動機付けと内発的動機付けです。
外発的動機付け
外発的動機付けというのは、外部から与えられる昇進や昇給などの報酬によるものです。
何を本人が外発的動機付け要因にしているかを判断することによって、マネジメントを効果的に行うこともできます。
外発的動機付けはすぐに効果が現れやすいものですが、持続性が無いこともあり、特に金銭的報酬においてこの傾向は顕著です。
内発的動機付け
内発的動機付けというのは、本人の内部から発生している好奇心や向上心、探求心などです。
内発的動機付けによる身近な行動としては、損得がない趣味の活動などがあります。
自分の内部にある楽しいからやる、やりたいためにやるというような意思が動機付けになって、行動に繋がります。
自分自身の内部に起きる達成感や充実感などが、内発的動機付けの報酬です。
そのため、個人によって内発的動機付けは違います。
例えば、成果を競争であげることがストレスになる人がいたり、喜びになる人がいたりします。
また、内発的動機付けは、何か目標を自分自身で決めて実行するという感覚にもなります。
他の人からのアプローチが難しいことが、内発的動機付けのデメリットです。
そのため、内発的動機付けは本人ができていないときの対処が難しいでしょう。
コーチング理論と動機付け理論の違いとは?
コーチング理論は、動機付け理論とよく間違いやすい考え方です。
コーチングは、周りからの影響ではなく内向的な「答えは自分自身の中にある」という考えに基づいて、自分を支援してくれる人との信頼関係を中心にしたコミュニケーションを展開します。
これをベースに、本人自身が目標やアイデアや新しい選択肢に気付き、行動を自発的に起こすことをサポートする方法です。
コーチング理論と動機付け理論は、「自らの行動を相手に促す」という共通点がありますが、アプローチ方法が活動を促すために違っています。
コーチング理論は、自分自身で考えることを重要視し、コミュニケーションを時間をかけて行ったり、定期的な1on1というような面談を通して継続的に行ったりすることが特徴です。
一方、動機付け理論は、部下に対して上長がマネジメントの範疇として行うことが多くあります。
動機付け理論のビジネスにおける上手な利用方法とは?
一般的に、動機付け理論は、自然に毎日のコミュニケーションの中で取り込まれていくものです。
ここでは、動機付け理論のビジネスにおける上手な利用方法についてご紹介します。
やる気を適切なコミュニケーションでアップさせる
多くの上長は、部下とのコミュニケーションに普段から気配りしているでしょう。
しかし、コミュニケーションがやる気をダウンしないようにしようというような守りのものであることも多くあります。
優れた上長は、部下を褒める時期がいつ来るかを常に最も優先して考えています。
予定以上の進捗のときや何か成功したときなどは、部下の承認欲求を手放しで褒めることによって満たし、次回も頑張ろうという気持ちにさせます。
フィードバックのチャンスを設けて承認欲求を満たす
また、部下とやり取りするときは、定期的にフィードバックのチャンスを設けることが大切です。
フィードバックのチャンスのときは、一方的に評価を伝えたり褒めたりしないで、お互いのコミュニケーションの場にするのがおすすめです。
部下は、上長に相談したい、聞いてもらいたいと思っています。
この気持ちを十分に汲み取って対応することが、動機付けの強いものになります。
意思決定において重要視するものを採用面接では聞く
動機付け理論を応用することが、新入社員を採用するときにも大切です。
戦力として入社した後に戦う仲間になるため、モチベーションをどのようなシーンでアップしているか、特に自分自身が意思を決定するときにどのようなことを重要視しているかを聞くことが大切です。
部下のモチベーションをアップする動機付けの方法は、これが正解であると示すのは非常に困難です。
しかし、社員ごとの正解が、一人ひとりの社員に着目して対話を重ねていくことによって見つかります。
上手く動機付け理論を利用し、成果を社員が出せる社内の仕組み作り、職場環境を目指すのがいいでしょう。
代表的な動機付け理論とは?
社員のモチベーションは、モチベーション理論を学ぶことによってアップさせることができます。
ここでは、代表的な動機付け理論についてご紹介します。
マズローの欲求5段階説
マズローの欲求5段階説は、人の欲求は5段階の生理的欲求、安全欲求、社会的欲求、尊厳欲求、自己実現欲求で構成されており、生理的欲求、安全欲求、社会的欲求の低次欲求が満たされれば、尊厳欲求、自己実現欲求の高次欲求を満たそうとする理論です。
ハーズバーグの動機付け衛生理論
ハーズバーグの動機付け衛生理論は、人の欲求は仕事に対する行動を自発的に起こそうとする動機付け要因と仕事に対する不満に繋がる衛生要因にわかれるという理論です。
動機付けを図るためには、社員の成功体験を多くし、昇進させたり責任のある仕事を与えたりすることが大切であるとしています。
マクレガーのX理論・Y理論
マクレガーのX理論は、命令されないと人は仕事をしないという考え方です。
一方、マクレガーのY理論は、条件次第で人は責任を持って、自発的に行動するという考え方です。
X理論、Y理論のいずれに偏っても、部下を管理するときは上手くいきません。
バランスよくX理論、Y理論を取り込むことが大切です。
アンダーファのERG理論
アンダーファのERG理論は、マズローの欲求5段階説をベースにして、生存欲求、関係欲求、成長欲求にわけたものです。
低次欲求が満たされれば高次欲求を満たそうとしますが、低次欲求が満たされなくても高次欲求を満たそうとしたり、同時に低次要求と高次欲求が存在したりすることもあるとしています。