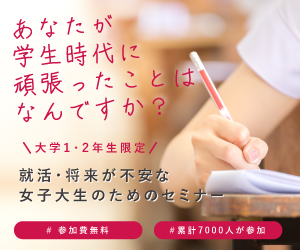「伯母」と「叔母」の違いとは?
「伯母」というのは、自分の親の姉にあたる人で、自分の親よりも年上の姉妹です。
一方、「叔母」というのは、自分の親の妹にあたる人で、自分の親よりも年下の姉妹です。
「伯母」と「叔母」の使い分け方とは?
ここでは、「伯母」と「叔母」の使い分け方についてご紹介します。
「伯母」は「叔母」より若いこともある
年齢に影響されることは、「伯母」と「叔母」の使い分けにはありません。
例えば、義妹の方が母の姉より年長でも、「伯母」が母の姉になり、「叔母」が義妹になります。
「伯母」と「叔母」の区分けの対象は、血族以外に、養子縁組や婚姻などによる姻族も含む傍系の三親等になるため、妹の方が姉より年長のこともあり得ます。
そのため、注意して年齢に惑わされないようにする必要があります。
未婚・既婚は「伯母」「叔母」に関係ない
「伯母」でも「叔母」でも、未婚の女性に対して「おば」という言葉を使うのは違和感があるでしょう。
しかし、父母や父母の姉あるいは妹のときは「伯母」「叔母」に未婚でもなり、子供が多くいた頃は「叔母」と本人の年齢が近いこともありました。
しかし、「おばさん」と呼ぶのは、「伯母」や「叔母」が若かったり未婚であったりするときははばかられるでしょう。
このようなときは、「お姉さん」という言葉を使ったり、名前で呼んだりしますが、「伯母」「叔母」を第三者に紹介するときには使います。
「伯母」と「叔母」を使った例文
関係性が「叔母」と「伯母」は違うのみであるため、大きな違いは基本的な使い方にありません。
ここでは、「伯母」と「叔母」を使った例文についてご紹介します。
「伯母」を使った例文
「伯母」を使った例文としては、次のようなものなどがあります。
- 「母は、自分と伯母の2人の姉妹だ。」
- 「父方の伯母は多くの子供がいるため、従兄弟が私には多い。」
- 「10歳以上母と伯母は離れており、高齢になっている。」
「叔母」を使った例文
「叔母」を使った例文としては、次のようなものなどがあります。
- 「両親が共稼ぎであったため、叔母さんの家によく遊びに行った。」
- 「父方には3人の叔母がおり、よくかわいがってくれる。」
- 「父の妹の叔母が、お正月になれば帰省する。」
「伯母」と「叔母」の使い分けが必要なシーン
親族が集まる葬儀や結婚式などでは、「伯母」と「叔母」の使い分けが必要になります。
ここでは、「伯母」と「叔母」の使い分けが必要なシーンについてご紹介します。
年賀状や手紙
文字に表す年賀状や手紙などのときは、「伯母」と「叔母」の使い分けが必要です。
「伯母」と「叔母」は、もともと自分の親の姉妹になるため、目上になります。
そのため、年賀状や手紙を書くときは、自分と「おば」との年齢差や自分と「おば」との親しさなどによっても違うため一律ではありませんが、目上の方に出すものであるため、一般的に敬語を使って失礼の無いようにします。
親しく普段は話をしていても、年賀状や手紙では敬語をきちんと使うようにしましょう。
葬儀
葬儀のときは、親族の席に「おば」は座ります。
親族の席は、上座が前列の祭壇に近い方になります。
故人と深い縁のあった順番に、上座から座っていきます。
故人と深い縁のあった人から、お焼香の順番もなります。
例えば、自分の「祖父」の葬儀のときは、「おば」のみの順番としては、「伯母」の次に「叔母」になります。
葬儀の席次については、「伯母」よりも「叔母」の方が下座になります。
結婚式
結婚式の席次表は、「伯母」と「叔母」の使い分けが必要です。
目上の方へのおもてなしや敬意の意味が結婚式の席次には込められており、「伯母」と「叔母」を正しく使い分ける必要があります。
結婚式のときは、濃い血縁関係の方が末席になります。
最も上座は、新郎新婦になります。
末席から順番に、両家の両親、新郎新婦の「兄弟姉妹」「祖父母」になり、この後に「伯父」「伯母」「叔父」「叔母」になります。
「伯母」の方が「叔母」よりも末席になります。
「伯母」と「叔母」に関係する言葉
「伯母」と「叔母」は、親の姉と妹を表現する言葉です。
親族を表現する言葉は「伯母」と「叔母」以外にもいくつかあるため、一緒に把握しておきましょう。
ここでは、「伯母」と「叔母」に関係する言葉についてご紹介します。
「伯父(おじ)」「叔父(おじ)」
「伯父(おじ)」「叔父(おじ)」は、親の兄弟です。
「伯父」は親の兄、「叔父」は親の弟です。
「従兄弟(いとこ)」「従姉妹(いとこ)」
「従兄弟(いとこ)」は男のいとこで、「従姉妹(いとこ)」は女のいとこです。
「いとこ」は、「伯父」や「叔父」、「伯母」や「叔母」の子供です。
年上の「従兄弟」を「従兄(じゅうけい)」、年下の「従兄弟」を「従弟(じゅうてい)」、年上の「従姉妹」を「従姉(じゅうし)」、年下の「従姉妹」を「従妹(じゅうまい)」ということもあります。
「従兄弟」や「従姉妹」は4親等になります。
民法においては、血が繋がっているときは親族になりますが、親族に結婚によってなった配偶者の血族のときは自分の親族にはなりません。
「大伯母(おおおば)」「大叔母(おおおば)」「従祖母(じゅうそぼ)」
「大伯母(おおおば)」は、親の「伯母」で、「祖父母」の姉になります。
「大叔母(おおおば)」は、親の「叔母」で、「祖父母」の妹になります。
同じように、「大伯父(おおおじ)」は親の「伯父」で、「大叔父(おおおじ)」は親の「叔父」になります。
なお、「従祖母(じゅうそぼ)」と「大伯母」や「大叔母」をいうこともあります。
「大伯母」や「大叔母」は4親等であるため、血が繋がっているときは親族になりますが、親族に結婚によってなった配偶者の血族のときは親族になりません。
「甥(おい)」「姪(めい)」
自分の兄弟姉妹の息子が「甥(おい)」で、自分の兄弟姉妹の娘が「姪(めい)」です。
自分の「伯母」や「叔母」からみれば、「甥」や「姪」に自分はなります。
「義甥(ぎせい)」や「義姪(ぎてつ)」は、配偶者の「甥」や「姪」になります。
「甥」や「姪」は3親等であるため、民法においては血族・姻族ともに親族になります。
「伯母」と「叔母」の英語表現とは?
「aunt」が、「伯母」と「叔母」の英語表現になります。
なお、「uncle」が「伯父」と「叔父」の英語表現になります。