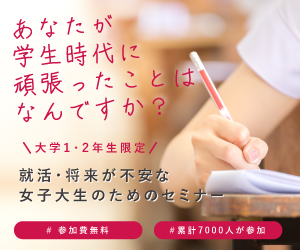「稟議」の意味とは?
「稟議」の読み方は「りんぎ」ですが、もともとの読み方は「ひんぎ」です。
「稟議」の「稟」の読み方は「リン」でもあるため誤った読み方の「りんぎ」が一般的に使われるようになって、現在の読み方は「りんぎ」になっています。
「稟議」の意味は、「官庁や企業などにおいて、採用したい案件があったときに会議を開催するほどではないときに、案件の内容を説明する書類を担当者が作って、関係する人に回して承認を求めることです。
そのため、会議を開催するほどではないような案件に関して、書類を作って関係する人に承認を求めることです。
「稟」の意味は「申し出る」ということで、「議」の意味は「相談する」ということです。
そのため、「稟議」の意味は、「申し出て相談する」ということになります。
「稟議」と「決裁」の違いとは?
「稟議」という言葉は、あまり耳にしたことがないのではないでしょうか。
しかし、「稟議」は「決裁」と同じような使い方をするため、どのような違いがあるかわかりにくいでしょう。
では、「稟議」と「決裁」はどのような違いがあるのでしょうか?
簡単にいうと、「稟議」は関係する人に案を回して承認を求めるという意味です。
「稟議」の詳しい意味は、次のようになっています。
- ・企業などで、会議を開催するほど大切でないことに関して、決定案を管理・管轄のメインになる主管者が作って関係する人に回して承認を求めること
- ・企業などで、重要な事項に関して、主管者が決定権のある役員などに決裁承認を書類で求めること
このように、「稟議」の意味は「決裁」と同じようなものであり、「決裁」する一つの方法であると考えるとよくわかるでしょう。
「稟議」をするときは、一般的に書類や電子媒体を使います。
「稟議」の書類は「稟議書」といいますが、企業によっては「起案書」「伺い書」「回議書」「立案書」などというときもあります。
また、基本的に「稟議」という言葉を使っていないような企業もあるでしょう。
「稟議」と「決裁」の違いとしては、どのようにその内容を取り扱うかということが挙げられます。
「稟議」はある程度の重い案件のとき使われることが多くありますが、「決裁」は軽い案件から重い案件まで使われることが多くあります。
また、「決裁」する人を一人に決めてしまえば、大きな案件になるほど大きな影響をその人の判断が与えるようになります。
しかし、多くの人の承認が必要な「稟議」にすると、審査がより幅広い立場からできるようになります。
企業によってこのような言葉をどのように取り扱うかは違っていますが、何人もの承認を求める「稟議」では「決済」がより慎重なものになります。
ここでは、「稟議」と「決裁」を使った例文についてご紹介します。
- 「彼は実績が十分にあるため、上長も彼の稟議については迷わないで通している。」
- 「20万円をオーバーするような物品を一月に買うときは、稟議にかける必要がある。」
この例文からわかるように、「稟議」の使い方としては「稟議に通る」「稟議にかける」などがあります。
「稟議に通る」の意味は承認されること、「稟議にかける」の意味は承認を求めることです。
- 「この案件は、上長の決裁さえもらうと実行できる。」
- 「話を上長の決裁なしで進めて失敗した。」
「稟議」のメリットとデメリットとは?
「稟議」の書類を作って、社内の何人かの承認を求める方法は、日本独特のものです。
日本で「合議制」が古くから重要視されている一つの名残です。
「稟議」によって、会議を開催するというような費用を低減することができます。
また、記録が書類で残るので、メリットとして事実をすぐにチェックができるということがあります。
しかし、「稟議」のときは、デメリットとして時間が最終的に承認されるまでにかかるということがあります。
現代のようにスピード感が要求されるビジネスシーンでは、ビジネスチャンスを「稟議」が通らないために逃すこともあります。
日本の会社は、外国の会社と比較して判断が速くないといわれている一因としては、このような「稟議」の制度が挙げられるでしょう。
また、何人かで承認をするため、トラブルが発生したときに責任がはっきりしないというデメリットもあります。
「稟議書」を書くコツとは?
「稟議書」というのは、「稟議」のときに使う書類です。
「稟議」とは、契約を結んだり、経費を使ったりするときなどに承認を関係する何人かに求めるための手続きです。
「稟議書」を書くときはコツがあり、漫然と書いていれば、「稟議」をせっかくしているにも関わらずなかなか通らないようになりかねません。
ここでは、「稟議書」を書くコツについてご紹介します。
結論をまず書く
日本の文章のときは最後に結論をよく書きますが、ビジネスシーンでは逆効果になります。
承認を求める関係する人は「稟議」にいくつも毎日対応しており、忙しいので「一目でわかること」が大切です。
申請理由や申請事項、コストパフォーマンスなどを、「稟議書」には書きます。
まず、しっかりと一文目に結論を書くようにしましょう。
よくある「稟議書」は、長々と想いや背景などを書いて、最終的にどのようなことをいいたいのかわからないものです。
このような「稟議書」であればチェックする人も負担が大きくなり、承認にその分時間がかかったりして「稟議」が最終的に通らなかったりするなどがあります。
メリットとデメリットを書く
案件のメリットのみを、「稟議」を通したいために書くのは駄目です。
というのは、目先のことだけを考えて、判断を冷静に行っていないのではないかというイメージを与えるためです。
メリットとデメリットを必ず比べてから、やはりメリットが大きいと書くようにしましょう。
このときは、判断を主観的に行うのでなく、データの具体的なものも書くと説得力がより増します。
デメリットはカバーする
メリットをアピールするよりも、デメリットをカバーするようにしましょう。
「稟議書」を回す前に承認を求める人の立場に立って読んで、突っ込まれるような箇所に関しては前もって十分にフォローしておきましょう。
問われる前に問題がないことを前もって示すと、スムーズに「稟議書」も回ります。
数値データを具体的に使う
申請理由や申請事項、コストパフォーマンスに関して書くときは、可能な限り証拠になるような数値データを具体的に使う方が説得力はより増します。
例えば、書き方としては「作業量が低減できる」というよりも、「作業量が1ヶ月あたり50時間低減できる」という方がメリットとしてはより伝わりやすいでしょう。