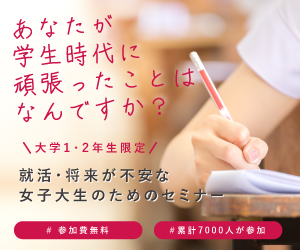「時短勤務」の意味とは?
「時短勤務」というのは、基本的に1日の所定労働時間を6時間以内にする育児短時間勤務などです。
育児・介護休業法においては、短時間勤務を条件をクリヤーした従業員が希望した時には、希望に応じる、あるいは代わりの措置を講じるように、事業者に対して要求しています。
「時短勤務」にはいろいろなスタイルがありますが、代表例としては次のようなものがあります。
- 所定労働時間を1日6時間までなどと短くする
- 子供を保育園に預けてから出勤できるように出社する時間を遅くする
- 保育施設の保育園などの終了時間に合わせて自宅に帰れるように、退社する時間を早くする
- 出勤する時間や退社する時間が変更できるフレックスタイム制を導入する
「時短勤務」の対象者とは?
ここでは、「時短勤務」の対象者についてご紹介します。
3歳未満の子供を養育している従業員
会社は、3歳未満の子供を養育している従業員に対して、所定労働時間を短くする措置を講じる必要があります。
「時短勤務」の概要は次のようになっています。
所定外労働の制限
3歳未満の子供を養育している従業員が残業の免除を子供を養育するために申し出た時は、会社は残業させては駄目です。
深夜の業務の制限
3歳未満の子供を養育している従業員が深夜の業務の免除を子供を養育するために申し出た時は、会社は22時~次の日の5時の深夜時間帯に業務をさせては駄目です。
3歳未満の子供を養育している従業員に対しては、基本的に1日の所定労働時間を6時間にする必要があります。
「時短勤務」がビジネスの性質などから困難な時は、次のような代わりの措置を講じる必要があります。
- 「育児休業に準じる措置」
- 「フレックスタイム制の導入」
- 「出社する時間の繰り下げ、退社する時間の繰り上げ」
- 「保育施設の事務所内への設置」
- 「短時間勤務」は、満3歳の誕生日に子供がなるまでの適用期間になっています。
3歳以上の小学校に入っていない子供を養育している従業員
会社は、3歳以上の小学校に入っていない子供を養育している従業員に対して、次のような措置を講じる必要があります。
時間外労働の制限
会社は、時間外労働を1ヶ月に24時間、1年間に150時間をオーバーしてさせては駄目です。
3歳未満の子供を養育している従業員とは違って、3歳以上の小学校に入っていない子供を養育している従業員に対して、会社は残業を条件付きで要求できるようになっています。
深夜の業務の制限
小学校に入っていない子供を養育している従業員が希望した時は、22時~次の日の5時の深夜時間帯に労働させては駄目です。
小学校に入っていない子供を養育している従業員に関する努力義務措置
小学校に入っていない子供を養育している従業員がいる時は、会社は次のようなことに対して努力する義務があります。
- 「育児休業に準じる措置」
- 「フレックスタイム制の措置」
- 「出社する時間の繰り下げ、退社する時間の繰り上げ」
- 「保育施設の事務所内への設置」
介護が必要な人が家庭にいる従業員
会社は、介護が必要な家族を持っている従業員に対して、次のような措置を講じる必要があります。
所定外労働の制限
残業の免除を家族の介護のために従業員が希望した時は、残業を会社はさせては駄目です。
深夜の業務の制限
深夜の業務が家族の介護のために困難な従業員に対しては、会社は22時~次の日の5時の深夜時間帯の業務をさせては駄目です。
所定労働時間の短縮
会社は家族の介護が必要な従業員に対して、次のような所定労働時間の短縮などの措置を講じる必要があります。
- 「所定労働時間の短縮」
- 「フレックスタイム制の導入」
- 「出社する時間の繰り下げ、退社する時間の繰り上げ」
- 「介護サービスの費用の援助」
「時短勤務」のメリットとは?
ここでは、「時短勤務」のメリットについてご紹介します。
生活に余裕が生まれる
「時短勤務」によって生活に余裕が生まれるようになって、容易にワークライフバランスが実現できるようになります。
公共施設や病院などは、17時までの業務というようなところも多くあります。
そのため、退社が16時にできるのであれば、このようなところに行ったり、子供を余裕を持って迎えに行ったりすることができるでしょう。
人材が確保できる
「時短勤務」を導入することによって、仕事と介護や育児の両立というようなことが可能になります。
そのため、出産によって女性が諦めがちであった「キャリアの継続」が可能になるでしょう。
このようなことによってワークライフバランスが実現できると、従業員の不本意な離職を防止することができます。
人材の確保に、「時短勤務」の導入が繋がります。
生活パターンの改善も、「時短勤務」を導入することによって取り組みやすくなります。
子供と向かい合う時間が、仕事を継続しながら多くなることは大きなメリットでしょう。
「時短勤務」のデメリットとは?
ここでは、「時短勤務」のデメリットについてご紹介しましょう。
収入が少なくなる
「時短勤務」は、収入、給与についての不安が多くあることがデメリットです。
不利益な取り扱いを禁じている条例が育児・介護休業法にはありますが、業務時間を短縮した分、給与を少なくすることは法律には違反しません。
つまり、給与を短縮された時間に対して保障するのは決められていません。
従業員は、時間が短縮になった分の給与が差し引きされることに注意しましょう。
全力を仕事に注げない
「時短勤務」の時は、他の人に比較して仕事にかける時間が短くなります。
自分がメインになって行いたい仕事があっても、思い切り時間の都合で仕事ができなく、最終的に諦めるようになるシーンもあるでしょう。
「時短勤務」を導入する時に注意することとは?
ここでは、「時短勤務」を導入する時に注意することについてご紹介します。
不利益な取り扱い
不利益な取り扱いを「時短勤務」を申し出た従業員に対してすることを、育児・介護休業法では禁止しています。
不利益な取り扱いというのは、会社が従業員に対して降格や解雇、雇止めなどの不利益をもたらすことです。
就業規則
会社は、「時短勤務」の内容や手続きを明確に就業規則などに書いて、しかも従業員にこの内容を周知する必要があります。
例えば、新人研修の時などに、「時短勤務」の内容について周知しましょう。
要望が従業員からあった時に、再度説明するようなことも効果があります。
手続き
「時短勤務」の手続きは、基本的に、会社側で決めることができます。
この時は、手続きが複雑であるため申請を止めないようにする気配りが必要です。
所定外労働の制限や育児休業など、別の制度の手続きを参考にしながら決めましょう。