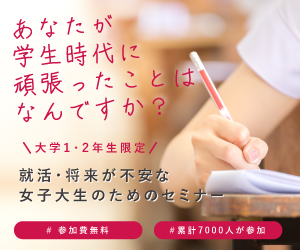「ワークシェアリング」の意味とは?
「ワークシェアリング」というのは、一人当たりの労働者が働く時間を短くすることで、全体の社会の雇用者数を多くしようとするものです。
すでに、オランダやフランス、ドイツなどでは「ワークシェアリング」が導入されており、オランダでは特に大幅に失業率が下がっています。
「ワークシェアリング」が生まれたのは、労働市場が悪くなって労働者の過労死が問題になっているためです。
一方、自殺が失業によって多くなるなどもあり、「ワークシェアリング」を雇用問題を解決する方法として使おうという意識になってきています。
「ワークシェアリング」は、仕事を分かち合って労働時間を短くすることによって、雇用が生まれ、産業構造の転換や労働流動化によって、全体の経済の安定を図るものです。
日本で「ワークシェアリング」を導入するときの課題とは?
ここでは、日本で「ワークシェアリング」を導入するときの課題についてご紹介します。
一人ひとりの従業員の仕事の役割や内容がはっきりしていない
外国においては、一人ひとりの従業員の仕事の役割、内容、目標などがはっきりしているので、スムーズに仕事のシェアが行えます。
しかし、日本においては、これらがはっきりしていないときがあり、仕事を分け合うのが困難です。
労働時間が短くなることで給料が少なくなる
「ワークシェアリング」を導入すれば、労働者の給料が少なくなることが考えられます。
そのため、一人ひとりの従業員に会社は別途手当などを支給します。
しかし、最終的に経費がワークシェアリングを導入する前よりかかるときもあるため、導入しない方がいいという判断になるときもあるでしょう。
正社員と非正規社員の給料の違いが大きい
日本では、正社員と非正社員の給料の違いが大きいので、正社員が短い労働時間になって、非正社員の労働時間と同じようになれば、給料などが違うようになります。
ワークシェアリングのメリットとは?
日本人の一人当たりの労働者時間は、圧倒的に長くなっていましたが、改正労働基準法が1988年に改正されたことによって着実に短くなっており、アメリカに次いで2位にまで2014年には短くなっています。
しかし、長時間労働者の比率に関しては、2000年の約28%から2014年の約21%に下がっていますが、第2位のアメリカの約17%とは大きな開きがあります。
長時間労働の国であると日本はいわれていますが、会社で仕事をする正社員のときは他の人などを見れば多くの人が納得するでしょう。
「ワークシェアリング」は、 仕事を分かち合うため、働いている時間が長い人は労働時間が短くなり、仕事を探している人は仕事が見つかり、雇用が生まれることがメリットです。
また、「ワークシェアリング」が成功すると、女性の社会進出や高齢者の雇用にもメリットが大きいでしょう。
給料が少なくなることがある
「ワークシェアリング」は、労働時間が短くなることによって、給料が少なくなることもあります。
もっと長い時間働いて儲けたいというような人は不満を持つリスクがあります。
そのため、「ワークシェアリング」では、給料に対する対策を従業員が反発しないように一緒に進めるときも多くあります。
生産性が悪くなることもある
労働時間を短くして、従業員の多くが仕事を分担するときは、従業員同士で引継ぎする必要があります。
しかし、上手く引継ぎができなければ、生産性が悪くなることもあります。
従業員も仕事のやりにくさを感じるので、モチベーションが下がるときもあるようです。
会社側の支出が多くなることもある
雇用が「ワークシェアリング」によって多くなったときは、その分給料や社会保障費が多くなることもあります。
雇用が生まれて社会に貢献しても、最終的に会社が苦しくならないように計画することが大切です。
「ワークシェアリング」の目的とは?
「ワークシェアリング」は、働く人の労働時間を短くして、仕事を分かち合うことによる雇用の安定化と創出が目的です。
「ワークシェアリング」によって、今まで仕事がなかった人を含めて、そのスキルに応じて誰もが働ける職場環境が整備されます。
「ワークシェアリング」を厚生労働省は次のような類型に分けて、意義をそれぞれ個別に持たせることによって、いろいろな角度から雇用の安定化と創出を図っています。
雇用維持型
すでに働いている人の解雇を防ぐため、仕事を従業員間でシェアするものです。
そのため、一部の従業員の過大な負荷が軽くなります。
雇用維持型
中高年層の一人あたりの従業員の労働時間を短くして、中高年層の雇用を確保し、雇用をより多く保つようにするものです。
主な目的は、中高年の余った人員を活かすことなどです。
雇用創出型
一人ひとりの労働時間を短くすることによって、雇用機会をより多くの人に与えるためのもので、主として失業率が高いことが慢性になっていることを解決します。
具体的には、法定労働時間を短くしたり、積極的に若年層を採用したりするなどがあります。
多様就業促進型
バリエーションを勤務の態様に設けることで、広く雇用機会を多くの人材に与えるものです。
高齢者や女性が働きやすい環境づくり、介護・育児と仕事の両立、有能な人材の確保が目的です。
具体的には、パートのフルタイム化などがあります。
外国の「ワークシェアリング」の事例とは?
「ワークシェアリング」は、オランダ、ドイツ、イギリスなどが導入しています。
例えば、早期退職制度を導入して、法定労働時間の短縮や雇用機会創出などを図っています。
「ワークシェアリング」に成功した事例としては、オランダがよく紹介されています。
オランダでは、「ワークシェアリング」が1980年代前半の大不況のときに大きく拡大しました。
特に、有名なものは1996年の「同一労働条件」の施策です。
この施策によって、パートタイム労働者とフルタイム労働者において、福利厚生や時給などに違いをつけることが禁止になりました。
これによって、労働者は自分の労働時間が決定できるようになりました。
日本と外国の「ワークシェアリング」が大きく違っているのは、その目的です。
外国においては「ワークシェアリング」の目的は雇用機会を創出することで、雇用を短時間労働勤務などで創出しています。
一方、日本においては、「ワークシェアリング」の目的は長時間労働を是正するために導入するときが多くあります。
そのため、労働時間を短くして人員を新しく雇うときに、社会保険や雇用保険というような費用がかかることが、「ワークシェアリング」がなかなか導入されない要因であるともいわれています。